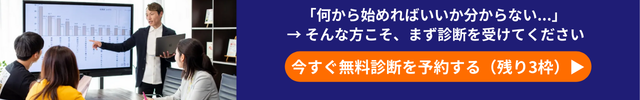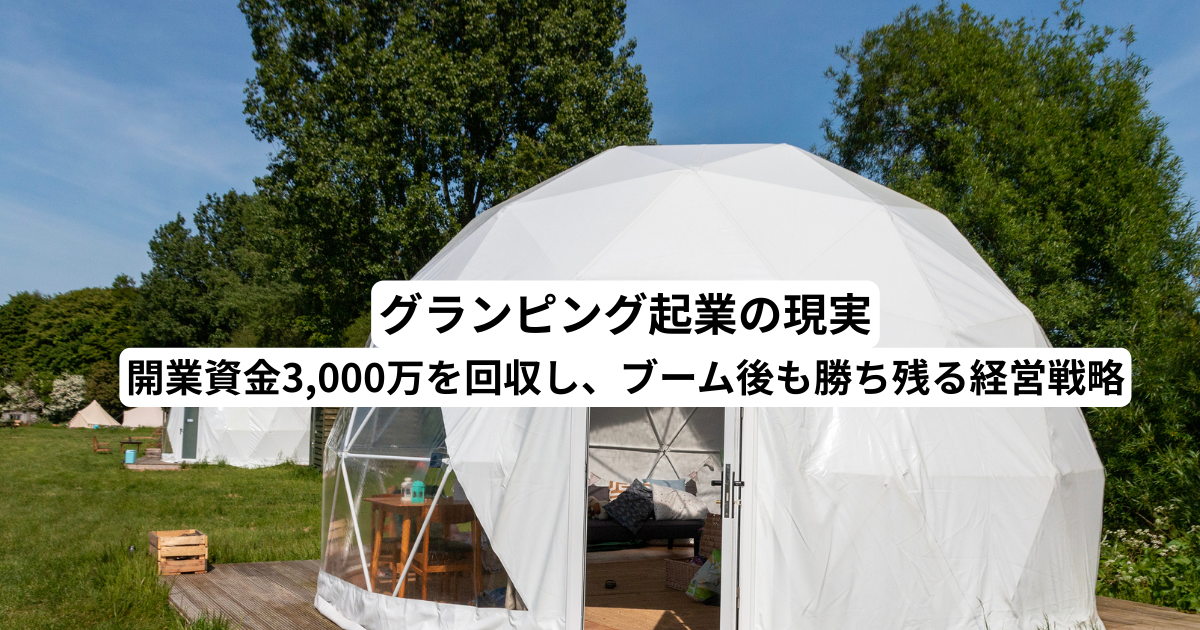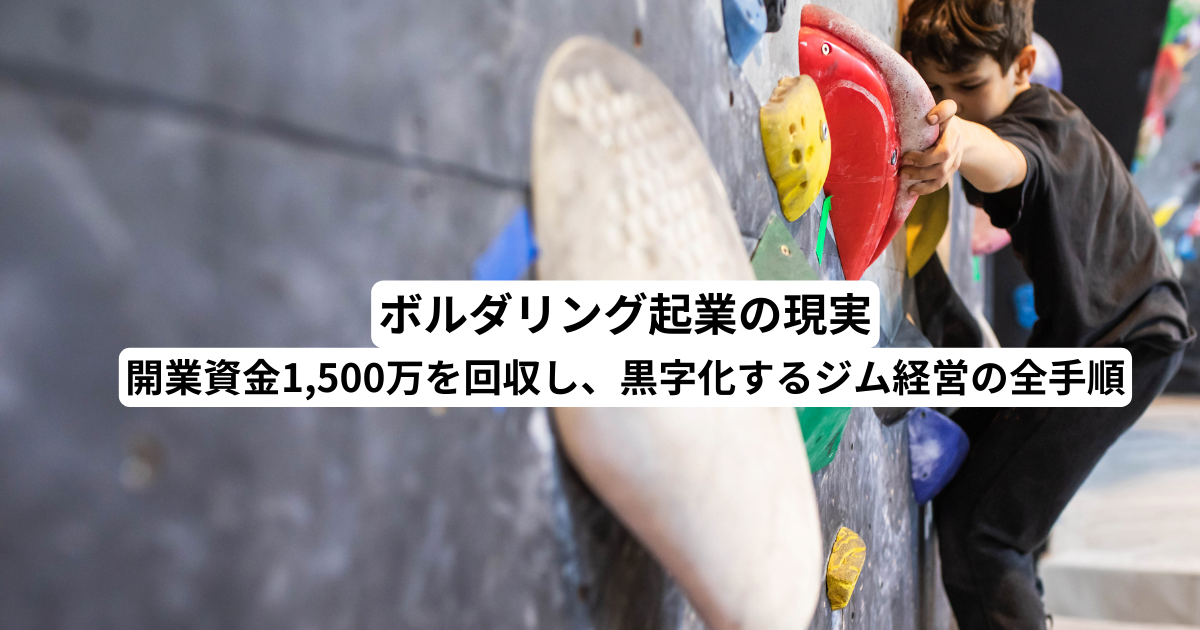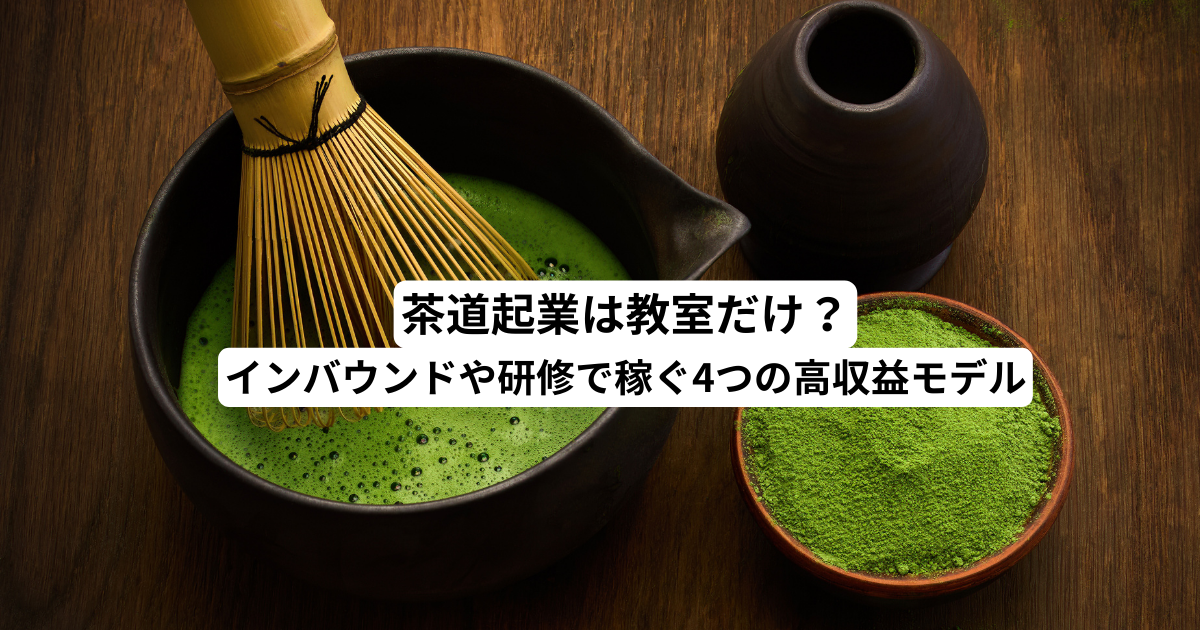2025.11.01 起業ガイド
料理での起業はやめたほうがいい?アイデア5選と失敗しない方法
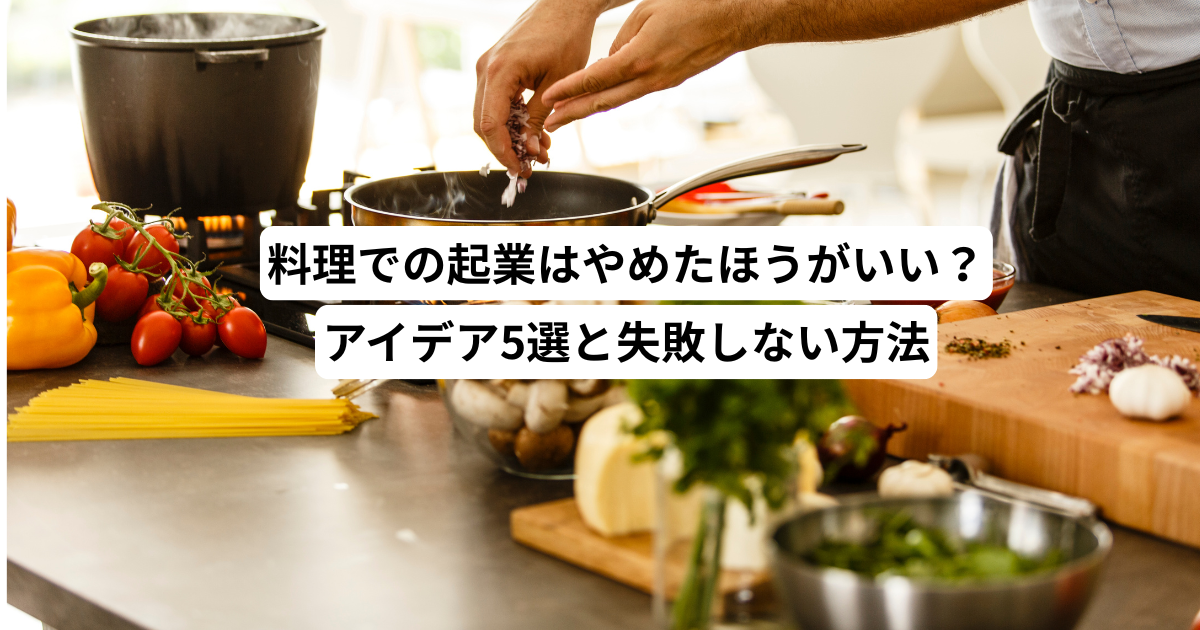
Index
「得意な料理を仕事にしたいけれど、今からでは難しいかもしれない」
「起業には多額の資金が必要で、失敗のリスクが怖い」
料理での起業に憧れつつも、資金や経験などを理由に、一歩を踏み出せないでいる方は少なくありません。
本記事では、料理分野の起業でよくある悩みや不安を解消し、起業後に後悔しない方法を解説します。
記事を読んだ後には、あなたに合った低リスクな起業の形が見つかり、夢を現実に変えるための具体的な方法が明確になります。
料理での起業が注目される3つの理由
近年、30代から50代が新しいキャリアとして料理での起業に注目しています。
働き方が多様化し、個人の経験が価値となる今、自身のスキルを活かすことが有力な選択肢となるからです。
ここでは具体的な3つの理由を解説します。
1. 低リスクで始められる手軽さ
料理起業の魅力は少ない資金で始められる点です。
一般的な飲食店開業と違い、自宅やオンラインを活用すれば、物件取得費などの高額な初期投資を抑えられます。
会社員や主婦の方が副業として挑戦する場合でも、金銭的なリスクが少ないため、起業しやすいのが特徴です。
2. 趣味や経験を活かせる働き方の新しい形
自分で培った料理スキルは、ほかにはない食の知識です。
子育てで得た時短レシピや健康管理の知識は、同じ悩みを持つお客様の役に立ちます。
自身の経験を元にしたサービスは独自性が高く、お客様からの共感も得やすくなります。
「ありがとう」の感謝の言葉が直接届き、やりがいを感じられます。
3. リモートワーク普及による働き方の多様化
リモートワークが普及し、働き手は自宅時間が増え副業を始めやすくなりました。
一方、消費者は「おうち時間」の食事を充実させたいと考え、質の高いテイクアウトやオンライン料理教室への需要が高まっています。
近年の物価高も影響し、社会を取り巻く環境が、料理での起業を後押しする大きなチャンスです。
料理で始める起業アイデア5選【スモールスタート編】
料理での起業はレストラン経営だけではありません。
大きな投資をせず、小さく事業を始めたい方に、5つの事業アイデアを紹介します。
自分のスキルやライフスタイルと照らし合わせ、「これならできそう」と思えるビジネスモデルをどのように実現するかを考えます。
1. 自宅を利用した対面やオンラインの料理教室
自宅のキッチンを活用する料理教室は、少ない設備投資で始められる手軽なアイデアです。
自身が持つ得意なジャンルを活かし、少人数制の対面レッスンやオンラインレッスンを提供します。
オンラインなら全国から生徒を集めることも可能で、コンセプトを絞れば独自の強みを発揮できます。
2. お弁当・惣菜のテイクアウト販売
地域に根ざしたビジネスとして、お弁当やお惣菜のテイクアウト販売も有力です。
自宅キッチンを改装するか、小規模な厨房を借りて始めます。近隣の住民やオフィスワーカーをターゲットに、健康的で家庭的なメニューを提供すれば、リピーターの獲得が期待できます。
3. オンラインで完結するレシピ販売・コンテンツ配信
物理的な商品を扱わないレシピのデジタル販売は、低リスクな方法です。
例えば、特定のテーマに沿ったレシピ集をPDFで作成し、noteなどのプラットフォームで販売します。
専門知識を求める顧客に、オンラインで直接価値を届けられるのが魅力です。デジタルなので在庫リスクがない点もメリットです。
4. キッチンカー・出張シェフ
店舗を持たずに移動しながら料理を提供できるのが、キッチンカーや出張シェフです。
キッチンカーはイベント会場やオフィス街など、人が集まる場所に出向いて販売できるのが強みです。
一方、出張シェフはお客様の自宅に伺い、記念日などの特別な食事を演出するため、固定店舗より初期費用を抑えられます。
5. フードブランド立ち上げ
特製のジャムやドレッシングなど、自身のレシピでオリジナル商品を開発し、フードブランドを立ち上げる方法です。自分のこだわりを形にできる起業スタイルといえます。
自分で製造許可を取得した工房で作るか、専門工場に製造を委託(OEM)します。
自分で作り上げたブランドの世界観を、オンラインショップやマルシェで発信し、ファンを獲得することも可能です。
「私にもできるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。
起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。
起業して人生を変えたい!と思う方は、まずはLINE登録をしてみてください。
料理での起業に必要な資格と届出
料理での起業には、法律で定められたルールを守ることが必要です。
お客様の安全に直結するため、資格の取得や行政への届出が義務付けられています。
事業を始めるために、具体的に何をすべきか、事前に確認しておきます。
「食品衛生責任者」は飲食店開業に必須の資格
食中毒などの事故を防ぎ、施設の衛生管理を徹底するため、食品を扱う施設ごとに1名以上の「食品衛生責任者」を置くことが法律で義務付けられています。
事業主は、各都道府県が開催する1日の養成講習会を受講すれば資格を取得できます。
開業準備の早い段階で、日程を確認し申し込むことが必要です。
「営業許可」は事業形態によって必要
提供する食品や営業形態に応じて、管轄の保健所から「営業許可」を取得する必要があります。
これは、施設が衛生基準を公的に満たしていることを認めてもらう手続きです。
施設の構造にも細かい基準があるため、物件契約や工事の前に、図面を持参して保健所に事前に相談しておくことが重要です。
「調理師免許」は持っていると信頼性が高まる
「調理師免許」は、飲食店を開業するための必須資格ではありません。
法律上は、食品衛生責任者がいれば事業を始められます。
しかし、調理師免許は食の専門家であることの公的な証明となり、お客様からの信頼性を高める効果があります。講習免除のメリットもあるため、取得しておくと有利に働く場面が多いです。
「防火管理者」は店舗で開業するなら必要
店舗を構えて事業を行う場合、「防火管理者」の資格が必要になることがあります。これは火災による被害を防ぐための責任者です。
具体的には、お客様と従業員を合わせた収容人数が30人以上になる施設で選任が義務付けられており、消防署が実施する講習を受講すれば取得できます。
料理での起業で失敗しないための7ステップ
料理での起業を成功させるには、順序立てた準備が不可欠です。
失敗のリスクを減らし、事業の土台を固めるために、7つのステップを紹介します。
ステップ1:コンセプト設計「誰に、何を、どう届けるか」
ビジネスの出発点は、コンセプト設計です。事業の核である「誰に、どのような価値を、どう提供するのか」を明確にします。
コンセプトが曖昧だと、メニューや価格などあらゆる判断がぶれてしまいます。
起業の軸となる「なぜこの事業を始めたいのか」にもつながり、開業後のモチベーション維持に必要です。
ステップ2:事業計画の作成で飲食店経営の骨格を作る
コンセプトが固まったら、「事業計画書」を作成します。頭の中のアイデアを客観的に整理し、実現可能性を検証するための設計図です。
事業概要、商品、市場分析、販売戦略、そして収支計画などを盛り込みます。融資を受ける際にも必要不可欠な書類となります。
ステップ3:飲食店開業資金ゼロでもできる資金調達方法の検討
日本政策金融公庫の2023年度新規開業実態調査によると、「飲食店、宿泊業」で開業した人のうち、約3割(29.0%)は開業費用500万円未満でスタートしています。
自身の事業に必要な「初期投資」と、開業後しばらく売上がなくても事業を続けられる「運転資金」がいくらになるか、具体的に算出します。
「自己資金ゼロ」で始めるのは現実的ではないものの、これらの制度を賢く組み合わせることで、自己資金が少なくても、起業を実現することは十分に可能です。
ステップ4:必要な資格取得と許認可申請
事業計画と資金の目処が立ったら、法的な手続きを進めます。
「食品衛生責任者」の資格取得や、保健所への「営業許可」の申請準備を始めます。
特に営業許可は申請から取得まで時間がかかるため、オープン日から逆算して早めに行動することが重要です。
個人事業主として開業する場合は、税務署への「開業届」の提出も必要です。
ステップ5:看板メニューの開発
お店の顔となる「看板メニュー」の開発は、成功を左右します。
メニューは、コンセプトを象徴するものでなくてはなりません。
自分の提供したい価値がお客様に伝わるような一品を考えておきます。
美味しさはもちろん、原価計算と価格設定のバランス、効率的な調理工程も考慮することが重要です。
ステップ6:SNSでファンを作りテスト販売で反応を見る
開業前から、未来のお客様との接点を作っておくことは有効です。
InstagramなどのSNSを活用し、開業準備の様子や料理への想いなどを発信して、ファンを増やします。
可能であれば、マルシェ出店などでテスト販売を行い、お客様からの直接的なフィードバックを最終調整に活かします。
ステップ7:顧客の声を参考に改善を続ける
無事に開業したら、そこが新たなスタート地点です。
事業を長く継続させるためには、お客様の声に耳を傾け、サービスを改善し続ける姿勢が欠かせません。
アンケートやSNSでの口コミを積極的に収集し、良かった点は伸ばし、改善すべき点は素早く対応するサイクルが、リピーターを育てます。
料理での起業をやめたほうがいい人の特徴3つ
料理での起業は魅力的な挑戦ですが、誰もが成功できるわけではありません。
憧れだけで起業すると後悔する可能性もあります。
ミスマッチを防ぐために、一度立ち止まって考えてほしい3つの特徴を紹介します。
1. 「作ること」だけが好きで経営や数字の管理に興味がない人
料理での起業は「経営」そのものです。料理人であると同時に、経営者でなくてはなりません。
日々の売上管理、原価計算、経費管理といった数字の管理は、事業を継続させるための重要な仕事です。
どんぶり勘定では、知らないうちに赤字が膨らむ危険があるため、経営者としての自覚が求められます。
2. お客様からの厳しい意見やフィードバックに耐えられない人
心を込めて作った料理が、すべてのお客様に称賛されるとは限りません。
ときには、「味が合わない」といった厳しい意見やネガティブな口コミに直面することもあります。
そうした批判に感情的になることや、深く落ち込んだりする繊細すぎる気質だと、精神的に負担となります。批判を真摯に受け止め、改善につなげる冷静さが必要です。
3. 衛生管理や地道な清掃作業が苦手な人
料理を提供するビジネスでは、安全と衛生が基盤です。
万が一、食中毒事故を起こせば、お店の信用は一瞬で失われるため、事業主には衛生管理が求められます。
調理器具の洗浄・消毒や厨房の清掃といった地道な作業を面倒だと感じるなら、料理を扱う事業主としての資質に欠けているかもしれません。
まとめ:料理での起業で後悔しない「自分らしい働き方」を叶えよう
本記事では、料理での起業を考える方が、後悔しないための具体的な方法論を解説しました。
料理での起業は、オンラインの料理教室や週末だけのテイクアウト販売など、自分のライフスタイルや目標に合わせて、規模や形を柔軟に選ぶことが可能です。
大切なのは、情報を集めて満足するのではなく、まず「自分なら何ができるか」を考えることです。
本記事で紹介したステップを参考に、自分だけのコンセプトを考え、事業計画を練ることから始めてみてください。
「起業をするのにサポートがほしい」
「起業に必要なことを知りたい」
そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。
相談していただくと、起業して成功するために何をすれば良いのかがわかります。

◯関連記事
・【週末起業】キッチンカーは儲かる?失敗しない始め方とリアルな収支
・【起業して軌道に乗るまで】3年間のリアルな道のりと乗り越えるための全戦略