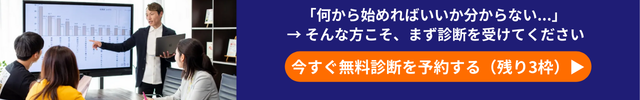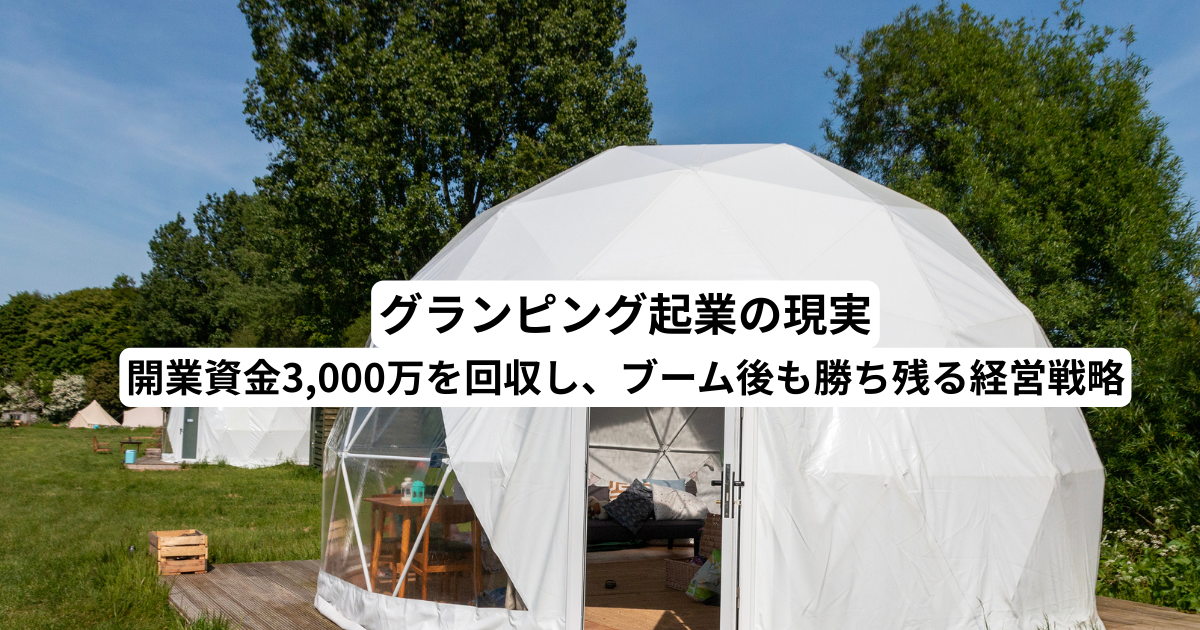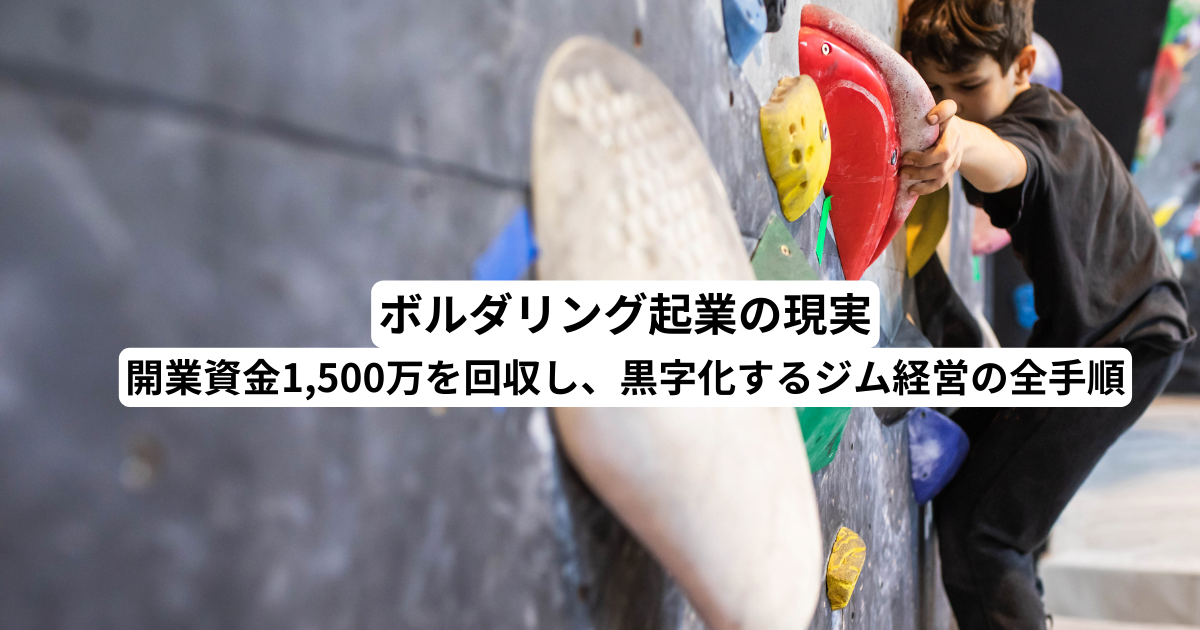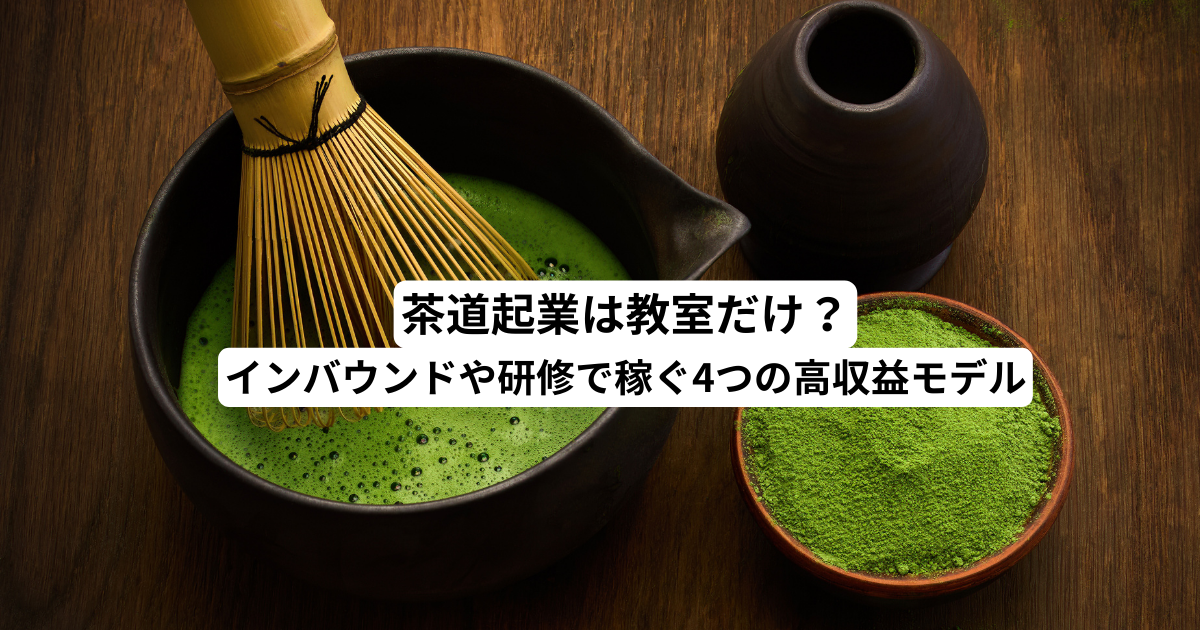2025.10.18 起業ガイド
福祉タクシーで起業|失敗しない開業と月収50万稼ぐ経営術

Index
行きたいところがあっても自由にいけない。
「そんな高齢者や障害者の助けになりたい!」と思い、福祉タクシーの起業を考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、そもそもどうやって起業をすればよいかわからなかったり、自分の事業が成功するかどうかも不安だったりしますよね。
そこで今回は、福祉タクシーの起業の方法やビジネスアイデア、成功するための具体的なステップを解説します。この記事を読めば、福祉タクシー起業でどのようなことをすればよいかがわかります。
なぜ今、福祉タクシーでの起業が社会に求められ、チャンスなのか?
高齢社会で大きな時代の追い風を受け、福祉タクシーは社会に求められており、ビジネスとして大きな可能性を秘めています。
なぜ福祉タクシーの起業がチャンスと言えるのか。その理由を3つ解説していきます。
超高齢社会の到来。「移動難民」の増加という深刻な社会課題
日本は、国民の4人に1人が65歳以上という、世界でも類を見ない超高齢社会に突入しています。
それに伴い、自身で車の運転ができない、公共交通機関の利用が困難といった移動難民が、都市部・地方を問わず急増しています。
高齢者の方にとって、通院や買い物、地域の交流といった当たり前の日常が、非常に困難なものになっています。
この深刻な社会課題を解決するのが福祉タクシーです。一過性のブームではなく、今後も常に需要があり続けるビジネスといえます。
大手では応えきれない、一人ひとりに寄り添う「個別ニーズ」への対応
大手タクシー会社も福祉車両を導入していますが、サービス内容はピンキリ。
利用者のニーズは、「車椅子ごと乗りたい」「通院の待ち時間、付き添ってほしい」「買い物の荷物持ちを手伝ってほしい」など、一人ひとり全く異なります。
個人経営の福祉タクシーだからこそ、細やかな個別ニーズに柔軟に対応できます。
マニュアルではない、心のこもったサービスを提供できるので、個人事業者の武器となります。
「介護保険外」サービスとの組み合わせで、高収益を目指せるビジネスモデル
福祉タクシーの収益はメーターで決まる運賃だけではありません。
通院時の院内介助や買い物同行、役所手続きの代行、冠婚葬祭や旅行の付き添いなど、介護保険外の自費サービスを組み合わせることで、客単価を引き上げることが可能です。
例えば、運賃が2,000円でも、2時間の院内介助(1時間3,000円×2時間)が加われば、合計8,000円の売上になります。
このように、単なる移動ではなく、利用者の外出全体をサポートする事業として設計すればで、社会貢献と高収益を両立させられます。
福祉タクシー起業、3つの許可形態とあなたが進むべき道
福祉タクシーの起業で、誰もが最初につまずくのが複雑な許認可制度です。
どの許可を取るかによって、対象となるお客様や提供できるサービスが大きく変わります。
ここでは、代表的な3つの許可形態を比較し、それぞれの特徴と、あなたがどの道を選ぶべきかの判断基準を分かりやすく解説します。
| 許可形態 | 根拠法 | 対象顧客 | 許可の難易度 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定) | 道路運送法 第4条 | 要介護・要支援認定者、障がい者、その他単独での移動が困難な人 | 高い | ・いわゆる「介護タクシー」の正式な許可 ・運賃は認可制で、介助料なども自由に設定可能 ・最もビジネスの自由度が高い |
| 自家用自動車有償運送事業 | 道路運送法 第78条 | NPO法人等の会員 | 中 | ・非営利活動が前提 ・運賃は実費の範囲内 ・NPO法人を設立する必要がある |
| 福祉有償運送 | 道路運送法 第79条 | 市町村に登録したNPO法人等の会員 | 中 | ・非営利活動が前提 ・運賃はタクシーの概ね半額が上限 ・運転者要件が比較的緩やか |
結論として、ビジネスとして本格的に収益を上げていきたいのであれば、目指すべきは「道路運送法 第4条許可」です。
手続きは1番複雑ですが、それに見合うだけの事業の自由度と収益性が得られます。手続き面で不安がある場合は、運輸業専門の行政書士に相談するのが確実で早い道です。
「起業について右も左もわからないのでサポートをしてほしい」
「自分のビジネスが失敗しないかどうかのアドバイスがほしい」
そんなお悩みの方もいるかと思います。スタートアップアカデミーでは、現在公式LINEから無料の起業相談を行っています。
起業相談を受けていただければ、どのように起業を進めて行けばよいかがクリアになります。ぜひお気軽にご相談ください。
9割が陥る「儲からない福祉タクシー」3つの罠
「福祉タクシーは社会貢献にはなるけど、儲からない」。そんな声を耳にしたことがあるかもしれません。
一部事実ですが、多くはビジネス上で失敗につながる罠にハマっているからです。典型的な3つの失敗パターンをご紹介します。
罠1:【低稼働率の罠】依頼を待つだけ。「待ち」の営業で車庫で待機する日々
福祉タクシーの仕事は、流しのタクシーのようにお客様が手を挙げてくれるわけではありません。
開業して、ただ電話が鳴るのを待っているだけでは、一日の大半を車庫で過ごすことになります。
特に平日の日中、通院利用が集中する時間帯以外をどう埋めるか。稼働率を上げるための営業戦略がなければ、事業は成り立ちません。
「いつか誰かが見つけてくれる」という待ちの姿勢では廃業へと近づきます。
罠2:【低単価の罠】「運賃」だけで稼ごうとし、介助料などの付加価値を取りこぼす
福祉タクシーの本当の価値は、単なる移動手段の提供ではありません。
車への乗降介助や階段の昇降、院内での付き添い、荷物持ちといった、利用者の困ったに寄り添う介助サービスにこそあります。
しかし、多くの事業者は、これらの介助サービスを無料の親切で行ってしまったり、あるいは遠慮して適切な料金を請求できていません。
運賃だけで利益を出すのは極めて困難です。
運賃以外の介助料という、正当な付加価値を収益の柱に据える発想がなければ、ボランティアと変わらなくなってしまいます。
罠3:【どんぶり勘定の罠】車両維持費や燃料費の管理が甘く、利益が残らない
個人事業主になると、会社員時代とは違い、お金の管理を全て自分で行わなければなりません。
特に福祉タクシーは、車両のローン返済や車検代、保険料、燃料費、駐車場代など、多くの固定費・変動費がかかります。
日々の売上に一喜一憂し、コスト管理をどんぶり勘定で行っていると、月末に計算してみたら「ほとんど利益が残っていなかった」という事態に陥ります。
毎日の売上と経費をきちんと記録し、月単位、年単位での収支を正確に把握する経営者としての計数感覚が不可欠です。
月収50万円を安定させる!福祉タクシー起業・成功ロードマップ5ステップ
では、どうすれば「儲からない罠」を回避し、社会に貢献しながら月収50万円以上を安定的に稼ぐことができるのでしょうか。
ここでは、持続可能な事業へと変えるための、具体的なロードマップを5つのステップで解説します。
ステップ1:【事業計画と資金調達】総額いくら必要?融資と補助金の賢い活用法
福祉タクシーの開業には、車両購入費を含め、総額で300万円~800万円程度の資金が必要となります。
まずは、車両費や事務所の賃料、駐車場代、各種許可申請費用、当面の運転資金(最低6ヶ月分の生活費+経費)などを詳細に算出し、事業計画書を作成します。
自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の「新規開業資金」などの創業融資を活用しましょう。車両についてはレンタルできると、大幅にコストを抑えられます。
ステップ2:【許可申請と資格取得】二種免許は必須?最短で開業するための手順
事業として運賃を収受するには、普通自動車第二種運転免許が必須です。
まだ持っていない場合は、最優先で取得しましょう。
また、利用者に直接触れる介助を行う場合、「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」以上の介護系資格も実質的に必要となります。
これらの資格を取得しつつ、運輸局への許可申請手続きを進めます。
申請書類も初心者ですと準備するのが大変なので、運輸業専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
ステップ3:【車両準備】新車?中古?福祉車両の賢い選び方と改造のポイント
事業の核となる福祉車両の準備です。
新車は高価ですが、故障のリスクが低く、最新の安全装備がついています。一方、中古車は初期投資を抑えられますが、状態の見極めが重要です。
リクライニング車椅子対応のスロープタイプか、ストレッチャーも乗せられるリフトタイプかなど、ターゲットとする顧客層によって選ぶべき車両は異なります。
車両メーカーのディーラーや、福祉車両専門店で実際に操作性を確認し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に選びましょう。
ステップ4:【仕事の取り方】ケアマネに選ばれる!「紹介が途切れない」営業術
福祉タクシーの仕事の多くは、病院のソーシャルワーカーや、地域のケアマネジャー(介護支援専門員)からの紹介で発生します。
したがって、彼らとの信頼関係構築が事業成功の鍵になります。
ただ名刺を置いてくるだけの営業ではなく、「〇〇(あなたの名前)さんは、認知症の方への対応が本当に丁寧で安心できる」「急な依頼にも嫌な顔一つせず対応してくれる」といった、あなたならではの強みや人柄を伝えるのが重要です。
しっかり営業できれば、困ったときに、真っ先に顔が思い浮かぶ存在になります。
定期的な訪問や情報提供で、地道に関係を築きましょう。
ステップ5:【収益最大化】運賃以外の「第二、第三の収益源」の作り方
運賃収入だけに頼らない、収益の柱を複数作りましょう。
まずは、明確な料金体系を定めた「介助サービスメニュー」を作成します。
例えば、「乗降介助:1,000円」「階段介助(1フロア):1,000円」「院内付添(30分):1,500円」といった形です。
これらを事前に丁寧に説明することで、お客様は納得して支払ってくれます。
さらに、買い物代行や薬の受け取り代行、あるいは地域の観光スポットを巡る「介護旅行」の企画など、利用者の「外出」にまつわるあらゆるニーズに応えることで、事業の幅を広げることが可能です。
まとめ:福祉タクシーとは、利用者の「希望」を運ぶ尊い仕事である
福祉タクシーの起業は、利用者の「もう一度、あの場所へ行きたい」という切実な夢や希望を叶えられる素敵なお仕事です。
この記事を参考に、まずはどのようなコンセプトで、福祉タクシーでどんなサービスを提供するかを考えてみましょう。
「起業のアイデアがまだ固まっていない」
「やりたいことは決まっているけど、どのように動いたらよいかわからない」
上記の悩みを持つ方もいると思います。
スタートアップアカデミーでは、現在公式LINEから無料の起業相談会を実施しています。
この無料相談会にご参加いただければ、どのように起業を進めていけばよいかがわかります。
◯関連記事
・【福祉で一人起業】アイデア5選|資格なしOK?資金と成功の秘訣
・【看護師の一人起業】アイデア7選|資格を活かして成功する5ステップ