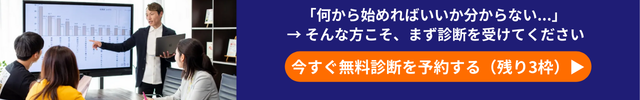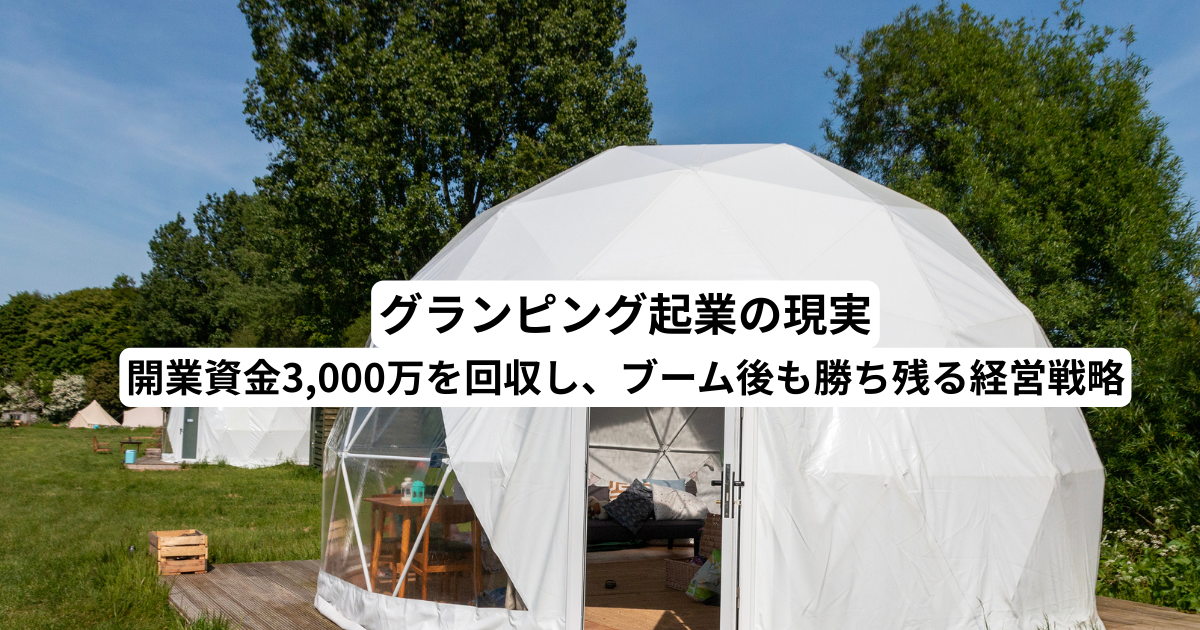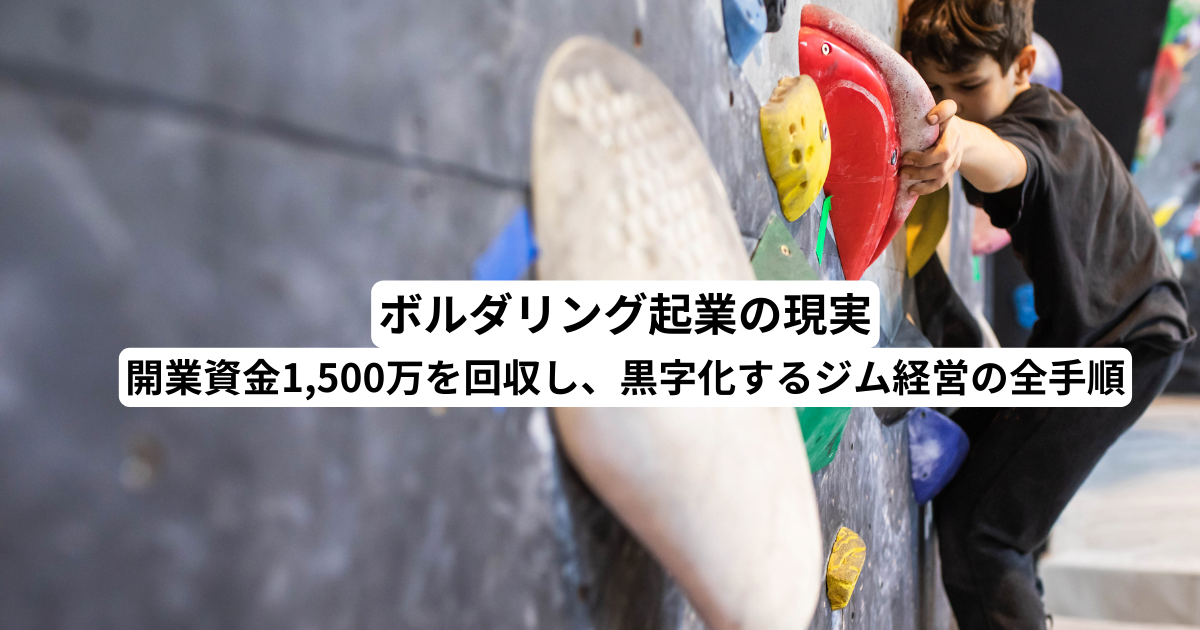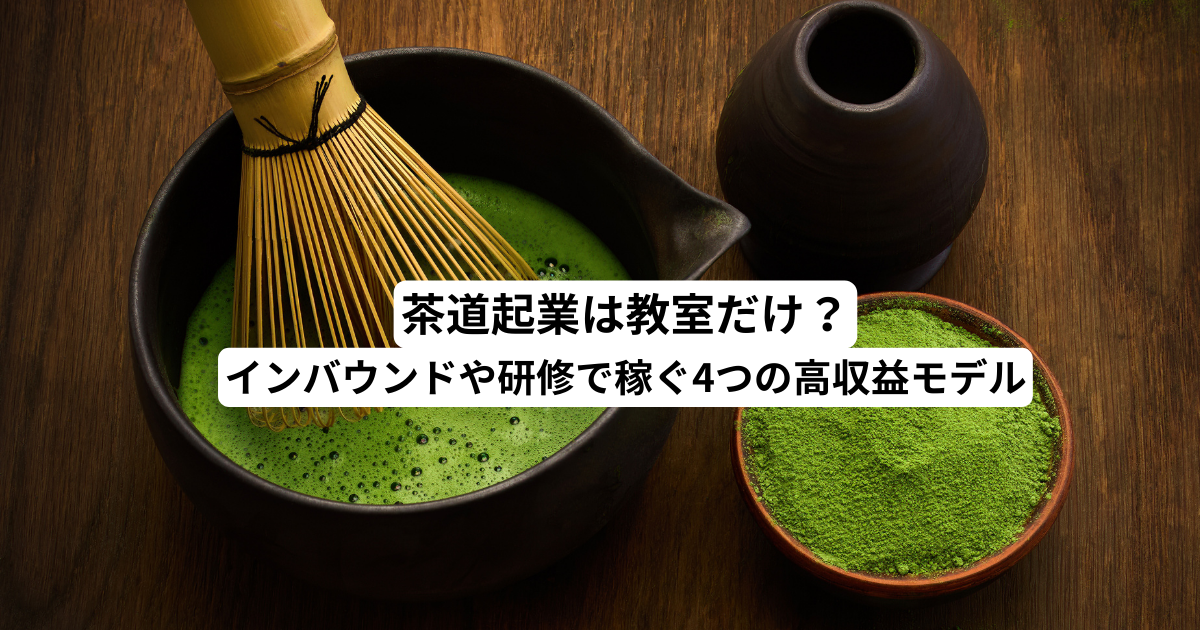2025.11.04 起業ガイド
「愛される」書店とは―地域密着×副業で始める4つの起業ステップ
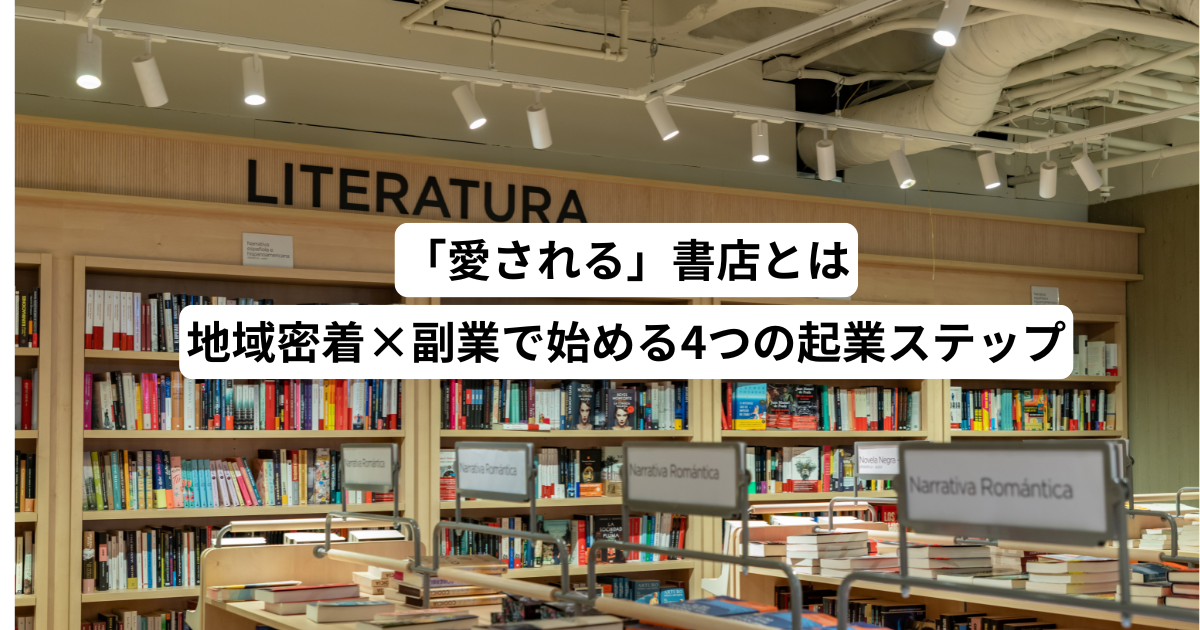
Index
あなたの思い出の書店は、今もありますか?
全国で書店が減り続けています。幼いころ通った店、学生時代に参考書を探した店。気づけば、シャッターが下りたままになっている。そんな光景を目にして、寂しさを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
「本屋を守りたい」「地域に本と触れ合える場所を残したい」
そう思っても、書店経営の専門家ではない自分に何ができるのか。資金や経験もなく、何から始めればいいのかも分からない。そう感じて、起業を諦めてしまった方もいるかもしれません。
しかし今、自宅の一角から副業のように始められる小規模経営の事例もあり、本が好きという気持ちを具体的に形にする道が開かれています。
今回は、書店業界の現状や書店を起業するメリット、必要な手続き、リスクを抑えた書店の始め方ステップを解説します。
あなたの本への愛、地域への愛を形にするヒントとして読んでみてください。
書店を起業する前に知っておくべき業界の動向
まずは、書店業界の現状をデータで確認します。
書店減少の現実と、今どのようなチャンスが生まれているのかを見ていきましょう。
全国書店数の減少
全国の書店数は、この20年で大きく変化しました。2003年に約21,000店あった書店は、2023年には約11,000店にまで減少し、20年で半減したことになります。
注目すべきは、「無書店自治体」の増加です。全国の約28%の自治体には、書店が1店舗も存在しません。地方を中心に、本を手に取る場所そのものが失われつつあります。
その一方で、大型チェーン店が撤退した地域では小規模でも地域に根ざした本屋が求められています。
経済産業省も「書店活性化プラン」を打ち出し、書店を地域の文化発信拠点として位置づけました。
空白地帯の市場と政策的支援
経済産業省が掲げる「書店活性化プラン」では、無書店地域での出店支援や、自治体との連携強化が明記されており、図書館や教育行政と連動し、地域の読書環境を整える動きが進んでいます。
背景には「子どもの読書離れ」という課題があり、全国学校図書館協議会の調査は、高校生の約半数が月に1冊も本を読んでいないというデータを発表しました。
この課題解決のため、行政は地域に本と触れ合う場を増やす必要性を訴えています。
この動きは、個人が小規模な書店を始める際の支援にもつながっています。
自治体によっては、空き店舗活用の補助金や、地域文化拠点としての運営支援が受けられるケースも増えており、制度面でも書店を始めやすい環境が整いつつあるといえます。
なぜ今「リアル本屋」が注目されているのか
オンライン書店が普及する一方で、リアル書店の価値が見直されています。
楽天ブックスの調査(2025)によると、約6割の読者が「ネットと実店舗を使い分けている」と回答しました。
その理由として挙げられるのが、
「実物を見たい」
「偶然の出会いを楽しみたい」
「スタッフの推薦を参考にしたい」
といった体験価値で、そうした価値はネットでは得られません。
特に小規模な書店では店主の個性やコンセプトが色濃く反映されるため、訪れる人にとって特別な場所となっています。この強みを活かせば、地域に愛される書店を育てることが可能です。
副業から書店を起業する3つのメリット-収入と自己実現の両立
次に、副業として書店を始めることでどんな利点があるのかを見ていきましょう。
収入面だけでなく、キャリアや自己実現という視点からも整理します。
メリット①:副業就業者の増加と国の施策
労働政策研究・研修機構の調査(2024)によると、副業を行う人が増えていることがわかります。
就業者6,700万人のうち約257万人、つまり3.8%が副業を行っており、男女別では、女性が7.4%、男性が5.1%という結果でした。
副業を始める動機としては、「収入を増やしたい」が54.5%、「生活を維持したい」が38.2%、「自己成長につなげたい」が18.7%となっています。
政府も「副業・兼業ガイドライン」で副業を推進しており、企業も副業を認める動きが広がっています。
メリット②:本業への影響
副業で書店を始めることは、収入の多様化にもつながります。
本業一本に依存するのではなく、別の収入源を持つことで経済的なリスクを分散できます。
また、書店を運営する過程で得られるスキルやネットワークは、本業へも還元可能です。
接客、仕入れ、在庫管理、SNS運用、地域連携を通じた経験は、キャリア全体の価値を高める要素になります。
メリット③:副業から自己実現へ
こうした流れの中で、「週末を副業にあてる」という選択肢が現実的に見えるようになってきました。
週末だけ、本業を続けながらもう一つの収入源と自己表現の場を持つ働き方が広がっています。
さらに、副業を行うことで転職の準備が可能です。
会社員として働きながら、自分のビジネスを小さく育てて将来的に独立する際の土台になります。
副業は、単なる収入源ではなく、長期的なキャリア戦略の一部として捉えることもできます。
◯関連記事
・週末起業とは?会社員が低リスクで始める成功の5ステップ
書店開業に向けて知っておくべき手続きと制度
実際に書店を開業する際にどんな手続きや制度を理解しておく必要があるのか。
法律や補助金の基礎を押さえておきましょう。
古物商許可(中古書販売時)
中古本を扱う場合、古物商許可が必要です。
手数料は地域によって異なりますが、東京都の場合は19,000円です。管轄の警察署に申請し、審査を経て許可が下ります。
新刊のみを扱う場合は、この許可は不要です。
ただし、古本やリサイクル本を仕入れる可能性がある場合は、事前に取得しておくと安心です。
申請から許可まで数週間かかることもあるため、余裕を持って準備しておきましょう。
独占禁止法と再販制度の基礎
書籍の価格設定には、「再販制度」を理解しておくことが必要です。
独占禁止法第23条第4項に基づき、新刊書籍は定価販売が義務付けられています。つまり、新刊を仕入れた場合、勝手に値引きして販売することはできません。
一方、古本や雑貨には再販制度が適用されないため、価格は自由に設定できます。この違いを理解しておかないと、知らずに違法行為をしてしまうリスクがあります。
再販制度は、出版文化を守るための仕組みですが、小規模書店にとっては価格競争ができないという側面もあります。
そのため、品揃えや接客、空間づくりで差別化を図ることが重要です。
補助金・支援制度の活用
中小企業庁が実施する「小規模事業者持続化補助金」で開業資金の一部を補助金でカバーできます。
この補助金は、販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者を対象としています。書店の場合、店舗の改装費や広告宣伝費、設備投資などが対象です。
また、商工会や自治体が独自に支援制度を設けているケースもありますので、開業を検討する地域の商工会に相談しましょう。
「私にもできるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。
起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。
「起業して本気で人生を変えたい!と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?
副業から始める書店-「地域密着」で愛される4つの起業ステップ
最後に、週末だけでも始められる具体的なステップを提示します。
リスクを最小限に抑えながら、自分に合った形を選び、段階的に発展させる道筋をご紹介します。
ステップ1:コンセプトを決める
愛される書店の特徴には、単に本を並べる「売場」ではなく、店主の世界観を提示する場としての機能があります。
なので起業の際は「誰に」「何を」「どんな体験で」届けるかというテーマを最初に決めるべきです。
例えば、「旅と写真の本屋」という形で旅行記や写真集を中心に扱い、顧客と旅の話ができる空間を作ったり、「育児と絵本の本屋」なら、親子が一緒に読める絵本を揃え、子どもが自由に過ごせる場を提供したり、といったテーマ特化が訪れる人の心に残ります。
経済産業省の「書店活性化プラン(2025)」でも、地域文化拠点としてのテーマ性を重視する方針が示されています。
コンセプト設計は、空間・立地・仕入れのすべてに影響する書店の土台です。
ステップ2:立地を選ぶ(自宅・築古物件・空き店舗など)
書店を成功させるためには「コストを抑えて継続できる場所」を選ぶことと、「自分の条件に合うスタート地点」を見つけることが重要です。
ここでは、3つの事例を紹介します。
・事例①【低リスク・低コスト型】自宅の一室を活用
書店にかかる家賃負担がなく、家族や生活圏との両立が容易です。東京の「本屋ロカンタン」は、マンションの一室を管理会社の許可を得て書店化した事例です。
DIYで内装を整え、生活感のない空間と店主の選書を軸に固定客を獲得しています。
・事例②【個性重視・リノベ型】倉庫や築古物件を改装
家賃を抑えつつ、空間の個性で勝負できる形です。東京の「Readin’ Writin’ BOOK STORE」は、元材木倉庫をリノベーションして開業しました。
高天井と梁を活かした内装で、「ベストセラーは置かない」というテーマが共感を呼び、イベント運営も好調です。
・事例③【地域密着・再生型】商店街の空き店舗・旧書店を再生
地域の信頼・人脈・ノウハウを継承できる形です。千葉の「noma books」は、旧大和屋書店の店舗を引き継ぎ、かつての顧客層を再来店させる仕組みを構築しました。
元店主の紹介で取次取引が継続できるため、仕入れハードルを大幅に軽減できます。
ステップ3:オンライン併用(リアル×ネットのハイブリッド)
週末だけの営業でも、オンラインを活用すれば平日も販売が可能です。実店舗+SNS+ECのハイブリッド運営により、在庫を効率化できます。
新刊情報や店主のおすすめを発信し、ECサイトで注文を受け付け週末に店頭受取や発送を行えば、地方に住んでいても全国に商圏を広げられます。
「選書紹介」など独自の世界観を発信することで、全国の共感者とつながり、リピーターを形成できます。
ステップ4:体験型への拡張(人が集まる場所へ)
小規模で始めた副業書店も、「物販+体験」の形で段階的に規模を拡張できます。
本の販売だけでなく、読書会やワークショップ開催、カフェや雑貨店の併設により、顧客の滞在時間を延ばし、地域の文化拠点としての役割を果たせます。
例えば東京の「PASSAGE by ALL REVIEWS」は本棚一つ一つに店主を設定する「運営参加型店舗」として人気を集め、また「パン屋の本屋」ではパン屋と書店の異業種コラボで親子連れのリピーターを獲得しています。
小さく始め、徐々に体験価値を追加していくという段階的な発展が、書店を持続可能なビジネスに育てる道筋といえます。
そしてこれらの事例でうかがえるのは、大型チェーン店にはない温かみと、店主の顔が見える安心感です。
小規模だからこそできる、地域との深いつながりの形成が次世代の書店の可能性といえます。
まとめ:地域に愛される書店を作ろう
全国で書店が減少する中、政府も書店を増やすための制度を整えており、地域には本屋が戻れる可能性が生まれています。
地域密着のコンセプトとオンラインの仕組みを併用しながら、あなた独自の書店の世界観を体験してもらいましょう。
まずは週末だけ、自宅の一角から。あなたの一歩が地域に新しい本との出会いを生み出すかもしれません。
「起業をするのにサポートがほしい」
「起業に必要なことを知りたい」
そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。
ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。
「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?

◯関連記事
・会社員の週末起業で人生を変える!成功するためのロードマップ
・【診断付】週末起業と副業の違いとは?あなたに合う稼ぎ方を見つける方法