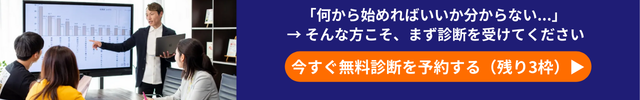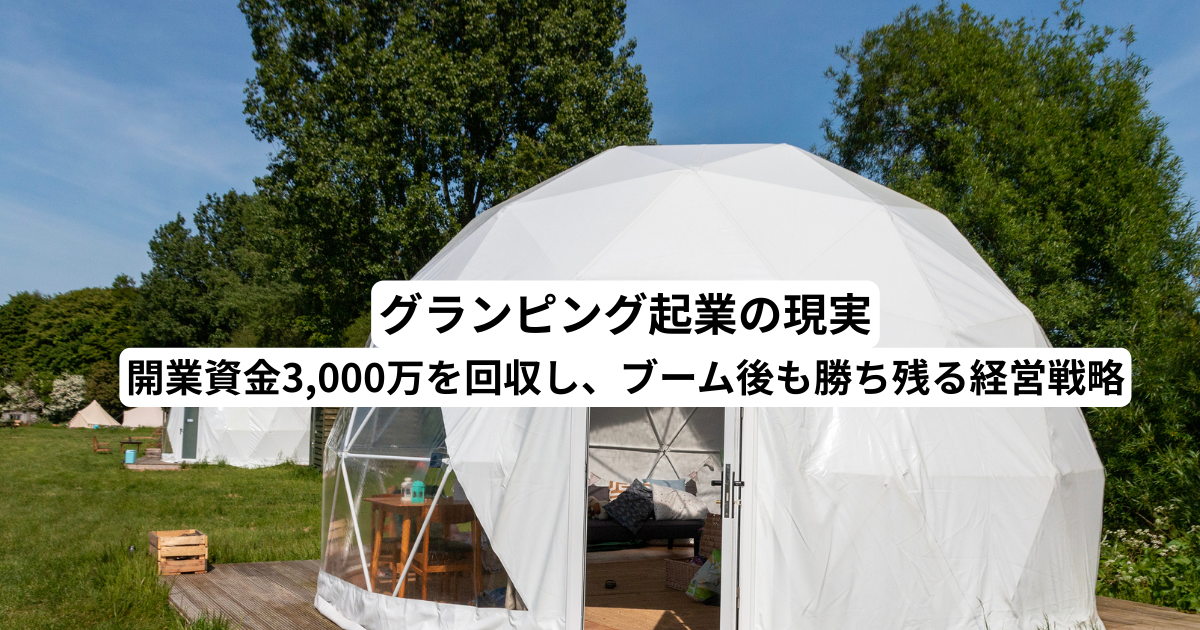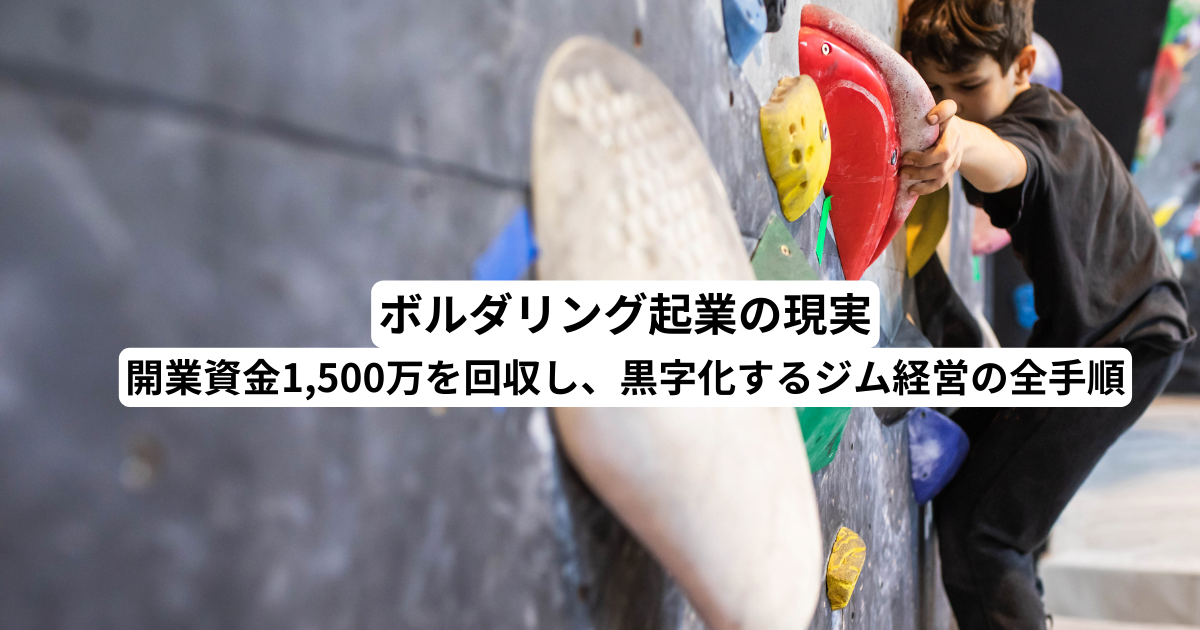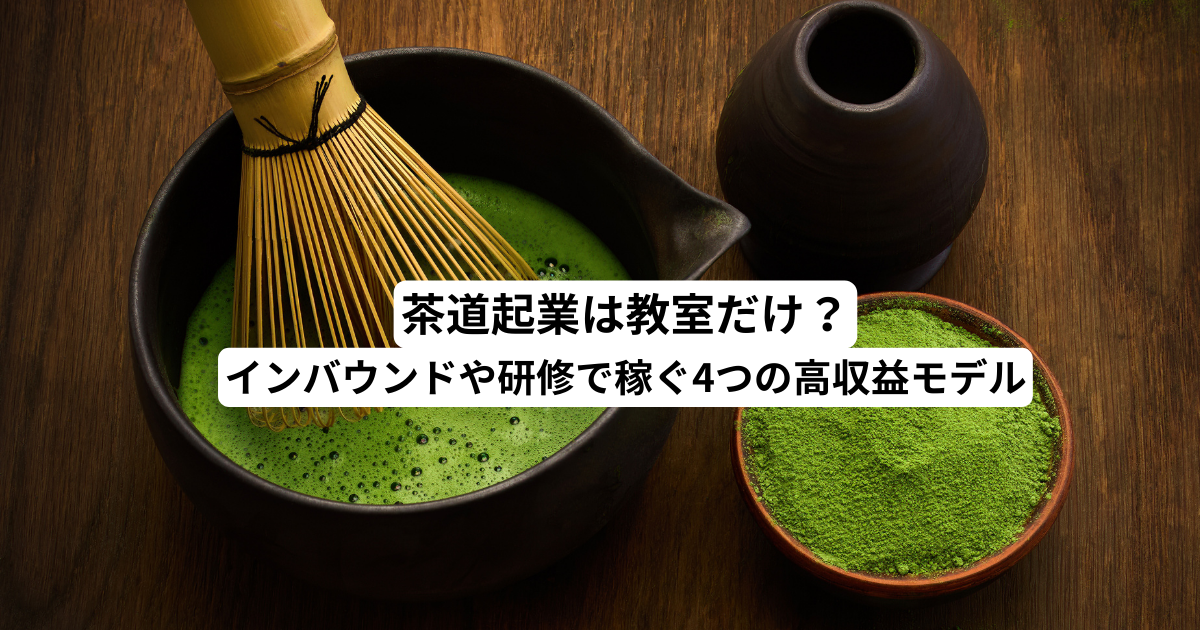2025.11.16 起業ガイド
配食サービスで起業!儲かる?失敗しない始め方と仕事の取り方

Index
「あなたのお弁当が、毎日の楽しみなのよ」。そんな感謝の言葉を直接受け取れる、社会貢献性の高い配食サービスでの起業。
超高齢社会の日本において、その需要はますます高まっています。配食サービスで起業をしたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、どのように起業をしたら良いかわからず、一歩踏み出せずにいませんか?
そこで今回は、配食サービスで起業する方法やビジネス戦略、成功するための具体的なステップを解説します。
本記事を読めば、配食サービスでの起業をどのように行えば良いかがわかります。
なぜ今、個人経営の「配食サービス」に大きなチャンスがあるのか?
「配食サービスは今から始めても、競争が激しそうだ」。
そうした不安を感じるかもしれません。しかし、個人経営の、心のこもった配食サービスに、強い追い風を吹かせています。
なぜ、今がこれほどまでにチャンスなのか。ビジネスとしての将来性を確信するための、3つの理由を解説します。
理由1:深刻化する「買い物難民」。地域の食を支えるインフラへ
スーパーが遠い、足腰が弱って買い物に行けない、重い荷物を持てない…。
様々な理由で、日々の食事の準備に困難を抱える「買い物難民」と呼ばれる高齢者は、全国に数百万人いると言われています。
彼らにとって、栄養バランスの取れた食事を、毎日決まった時間に届けてくれる配食サービスは、健康な生活を維持するためのライフラインです。
この切実で、巨大な社会課題の受け皿として、地域密着の配食サービスは、絶対になくならない需要に支えられています。
理由2:ただ届けるだけじゃない。「見守り」という、もう一つの重要な価値
配食サービスの本当の価値は、お弁当を届けることだけではありません。
毎日、同じ時間に同じ担当者が訪問することは、一人暮らしの高齢者にとって、貴重な「安否確認」の機会となります。
「変わりないですか?」という一言が、孤独感を和らげ、万が一の体調不良の早期発見にも繋がります。
この見守りの付加価値は、遠方で暮らすご家族にとっても、大きな安心材料となります。
大手ネットスーパーや、置き配型のサービスには決して真似のできない、この人間的な繋がりこそが、個人事業者の最大の武器です。
理由3:「冷凍弁当」では満たせない、「手作りの味」への根強い需要
市場には、工場で大量生産された安価な冷凍の配食弁当が溢れています。
しかし、多くの高齢者が本当に求めているのは、効率やコストではありません。
その土地の旬の食材を使い、人の手で心を込めて作られた、温かい「おふくろの味」です。
大手フランチャイズでは難しい、アレルギーへの個別対応や嫌いな食材の変更、味付けの濃さの調整といった、一人ひとりに寄り添った柔軟な対応ができること。
この「手作りの温かさ」と「柔軟性」こそが、個人経営の配食サービスが、高くても選ばれる理由となります。
あなたはどちらの道を行く?配食ビジネス起業「2つの選択肢」
配食サービスで起業するには、大きく分けて2つの道があります。
それは、既存のフランチャイズ(FC)に加盟する道と、完全に個人で独立開業する道です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの経験や資金力、目指す事業の形によって、どちらが最適かは異なります。
| 1. フランチャイズ(FC)加盟 | 2. 完全個人開業 | |
|---|---|---|
| メリット | ・ブランド力で信用を得やすい ・調理済み食材の供給や献立提供がある ・運営ノウハウの研修を受けられる |
・ロイヤリティがなく、利益率が高い ・献立や食材を自由に決められる ・独自のサービスを展開できる |
| デメリット | ・加盟金やロイヤリティが発生する ・献立の自由度が低く、「手作り感」を出しにくい ・本部の意向に左右される |
・食材の仕入れから献立作成、調理、配送まで全て自分で行う必要がある ・知名度ゼロから顧客開拓が必要 |
| おすすめな人 | 調理や経営が未経験で、まずは仕組みを学びながら堅実に始めたい人。 | 調理経験があり、「自分の味」で勝負したい人。経営の自由度を重視する人。 |
「起業をするのにサポートがほしい」
「起業に必要なことを知りたい」
そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。
ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。
「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?
9割が陥る「儲からない弁当屋」3つの罠と回避術
「毎日お弁当を作って配っているのに、なぜか手元にお金が残らない…」。
多くの個人経営の配食サービスが、この壁にぶつかり、疲弊していきます。
彼らが陥る失敗には、驚くほど共通したパターンがあります。
絶対に避けるべき3つの罠と具体的な回避術を解説します。
罠1:【価格設定の誤り】1食500円の壁。原価計算が甘く利益が残らない
多くの人が、「ワンコイン(500円)」という価格をつけがちです。
しかし、食材費や光熱費、包装資材費、あなたの人件費を正確に計算すると、1食500円では利益がほとんど残らない、という事実に気づきます。
回避術は、まず「1食あたりの目標利益額」を決めることです。
そこから逆算して、原価をコントロールし、自信を持って「1食700円」「800円」といった価格を設定するのが重要です。
あなたの手作りと見守りという価値は、決してワンコインで安売りしてはいけません。
罠2:【食品ロスの罠】日替わり献立にこだわり過ぎ、食材を無駄にする
「毎日違うお弁当で、お客様を飽きさせないように」という想いは素晴らしいですが、過度な日替わりメニューは、複雑な食材管理と大量の食品ロスを生み、経営を圧迫します。
回避術は、「週間固定メニュー」を基本とすることです。
例えば、「月曜は唐揚げ、火曜はサバの味噌煮…」とメニューを固定すれば、必要な食材の量を正確に予測でき、仕入れの無駄と廃棄ロスを劇的に減らせます。
その上で、季節の食材を使った「週替わり小鉢」などを加えることで、お客様を飽きさせない工夫は十分に可能です。
罠3:【待ちの営業】「美味しい」だけでは、ケアマネジャーは紹介してくれない
配食サービスの主な顧客紹介ルートは、地域のケアマネジャーです。
しかし、多くの事業者は、「美味しいお弁当を作っていれば、いつか評判が伝わるはずだ」と、紹介をただ待っているだけです。
多忙なケアマネジャーは、味はもちろんのこと、「アレルギー対応」「きざみ食・ミキサー食への対応」「緊急時の連絡体制」といった、信頼性と対応力を重視します。
回避術は、これらの「ケアマネジャーが求める情報」をまとめた分かりやすいパンフレットを作成し、定期的に訪問して、自社の強みを具体的に提案し続けることです。
月収50万円を安定させる!配食サービス起業・成功ロードマップ5ステップ
では、どうすれば「儲からない罠」を避け、社会に貢献しながら月収50万円以上を安定的に稼ぐことができるのでしょうか。
持続可能な儲かる事業へと変えるための、具体的なロードマップを5つのステップで解説します。
ステップ1:【事業計画と資金調達】厨房・車両の費用は?融資を引き出す収支計画
開業には、厨房設備の購入や営業許可の取得、配送用の車両、当面の運転資金など、自宅のキッチンを活用するとしても、最低でも200万円~300万円の資金が必要です。
自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の創業融資などを活用します。
融資審査の鍵を握るのが「事業計画書」です。
なぜこの地域で開業するのか(市場調査)、競合(大手FCや他の弁当屋)とどう差別化するのか、そして、1日の配達食数と単価から算出した売上予測と、食材原価や人件費を基にした詳細な「収支計画」を提示する必要があります。
ステップ2:【許可申請と資格】「飲食店営業許可」でOK?保健所への確認は必須
調理したお弁当を販売するには、食品衛生責任者の資格を取得し、管轄の保健所から「飲食店営業許可」または「そうざい製造業許可」を得る必要があります。
どちらの許可が必要かは、製造する量や販売形態によって自治体の判断が異なるため、必ず事前に保健所に相談しましょう。
施設の図面を持参し、「こういう形で、高齢者向けの配食サービスを始めたい」と具体的に説明し、必要な設備(シンクの数など)や手続きを確認することが、手戻りを防ぐための最も重要なポイントです。
ステップ3:【献立開発と仕入れ】利益を生む「定番メニュー」と、ロスを減らす仕入れ術
事業の利益率を左右する、献立開発と仕入れのステップです。
まずは、あなたの得意料理の中から、高齢者向けにアレンジした、栄養バランスと彩りの良い「定番メニュー」を1週間分、開発しましょう。
そのメニューに基づいて、必要な食材のリストと量を算出し、地域の業務用スーパーや八百屋など、安くて質の良い仕入れ先を開拓します。
重要なのは、いきなり完璧な日替わりメニューを目指すのではなく、まずはロスの出にくい「週間固定メニュー」で確実に利益を出す体制を構築することです。
ステップ4:【仕事の取り方】ケアマネに「あなたを指名させる」最強の営業ツールとは
仕事の獲得は、地域の居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属)や、地域包括支援センターへの営業が中心です。
ただ名刺を配るだけの営業では存在を知ってもらうのは難しいです。
ケアマネジャーにへの最強の営業ツールは、「試食弁当」と「事業所の強みが一目で分かるパンフレット」です。
心を込めて作ったお弁当を実際に食べてもらい、味を確かめてもらう。
そして、パンフレットで「きざみ食・ミキサー食・アレルギー対応可能」「管理栄養士監修」といった、他社にはない強みを具体的にアピールすることで、ケアマネジャーからの信頼を獲得できます。
ステップ5:【配送ルート設計】ガソリン代を節約し、配達件数を増やす「黄金ルート」の作り方
事業の利益を最大化するためには、配送の効率化が不可欠です。
Googleマップなどを活用し、顧客の住所を地図上にマッピングしましょう。
「どの順番で回れば、最も移動距離が短く、時間内に多くの件数を配達できるか」という、最適な「配送ルート」を設計します。
特に、顧客が増えてきたら、午前中に配達するエリアと、午後に配達するエリアを分けるなど、常にルートの見直しと最適化を行うことが重要です。
この地道な改善が、ガソリン代の節約と、1日あたりの配達可能件数の増加に繋がり、あなたの利益を押し上げます。
まとめ:配食サービスとは、地域の「温かい日常」を届ける仕事である
配食サービスの起業は、地域の高齢者の食生活という、命に直結するインフラを支え、日々の安否を見守り、何気ない会話を通じて心の繋がりを育めます。
あなたの作る温かいお弁当が、誰かの「当たり前の日常」を守る、大きな力になります。
ぜひこの記事を参考に、一歩踏み出してみませんか?
「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。
起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。
「起業して本気で人生を変えたい!」と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?
◯関連記事
・配達代行で起業!社会貢献もできる開業方法と手順を解説
・料理での起業はやめたほうがいい?アイデア5選と失敗しない方法