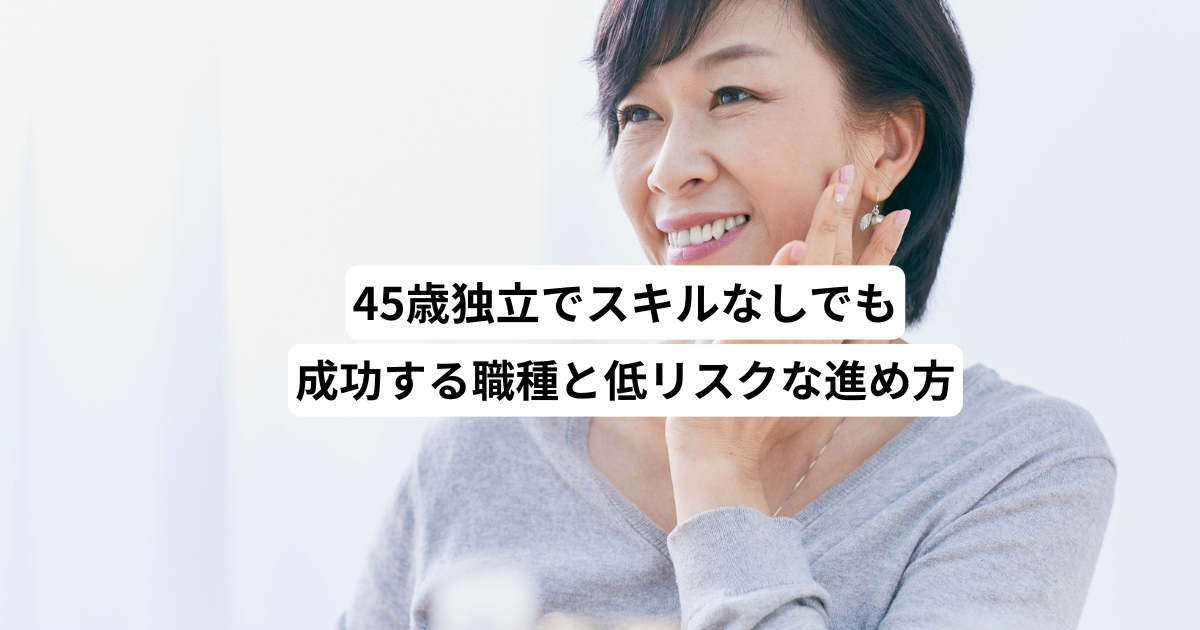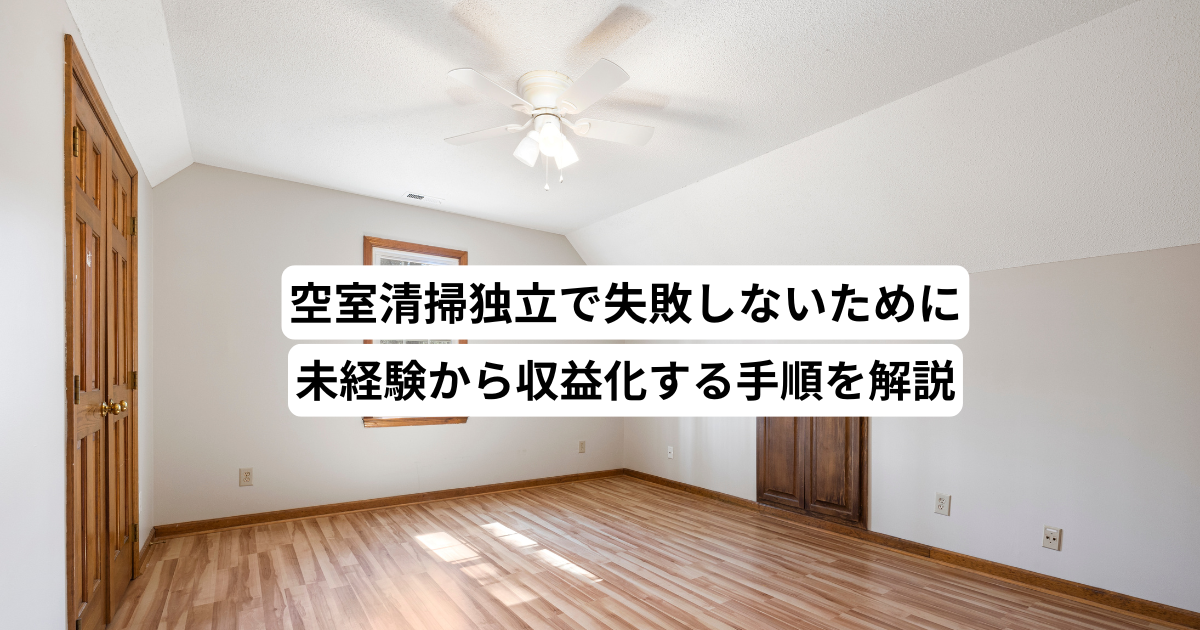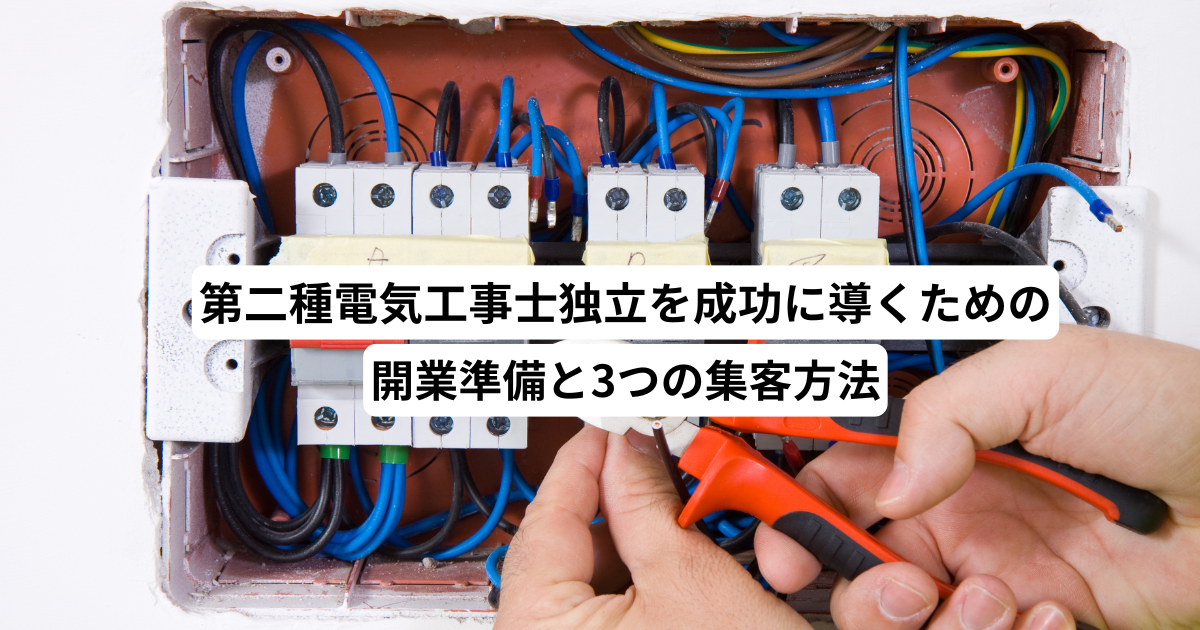2025.11.09 起業ガイド
移動スーパーで起業!儲かる?失敗しない始め方と仕事の取り方

Index
「あなたのおかげで、買い物ができて本当に助かるよ」。
そんな感謝の言葉を直接受け取れる、社会貢献性の高い移動スーパーでの起業。高齢社会の日本において、需要はますます高まっています。
しかし、その裏には「本当にビジネスとして食べていけるのか?」という、厳しい現実も存在します。
そこで今回は、今回は移動スーパー起業の方法や具体的なビジネスアイデア、成功までのステップを解説します。
この記事を読めば、移動スーパーでどのように起業をして事業を進めていけば良いかがわかります。
なぜ今、「移動スーパー」が社会に絶対必要とされるビジネスなのか?
「ネットスーパーもあるし、移動スーパーなんて必要なの?」そう思うかもしれません。
しかし、今、移動スーパーというビジネスに大きな需要が生まれています。必要とされる理由を3つ解説していきます。
理由1:700万人を超える「買い物難民」という深刻な社会課題
スーパーが近所にない、足腰が弱って遠くまで歩けない、車の運転ができない…。
様々な理由で、食料品など日常の買い物に困難を感じている「買い物難民」は、農林水産省の推計で全国に700万人以上いるとされています。
これは、地方の過疎地域だけの問題ではありません。都市部の坂の多い地域や、大規模団地でも深刻化しています。
移動スーパーは、地域のライフラインとしての役割を期待されています。
理由2:ただの物売りじゃない。「見守り」という、もう一つの重要な役割
移動スーパーの価値は、商品を届けることだけではありません。
週に数回、決まった時間に同じ場所を訪れる移動スーパーの販売員は、お客様である高齢者にとって、貴重な話し相手であり、社会との繋がりを感じられる存在です。
「〇〇さん、今日は顔色がいいね」「最近、変わりない?」といった何気ない会話が、孤独感を和らげます。
そして、この定時巡回は、地域社会の安否確認という、非常に重要な役割も担っています。
行政や地域包括支援センターとも連携する、この「見守り機能」こそ、大手ネットスーパーには決して真似できない、移動スーパーならではの付加価値です。
理由3. 大手スーパーも注目。地域社会と連携する「新しいインフラ」へ
移動スーパーは、個人商店が細々と行うイメージでした。
しかし現在では、買い物難民問題の深刻化を受け、大手スーパーマーケット自身が、地域貢献と新たな収益源として、移動スーパー事業に積極的に参入し始めています。
移動スーパーが、一過性のビジネスではなく、持続可能な社会インフラとして認知されたことを意味します。
そして、大手スーパーと提携し、その商品を販売する形のフランチャイズモデルが確立されたことで、個人でも、商品の仕入れリスクを抑えながら、成長市場に参入できる道が大きく開かれました。
あなたはどちらの道を選ぶ?移動スーパー起業「2つの選択肢」
移動スーパーで起業するには、大きく分けて2つの道があります。
既存のフランチャイズ(FC)に加盟する道と、完全に個人で独立開業する道です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの経験や資金力、目指す事業の形によって、どちらが最適かは異なります。
| 1. フランチャイズ(FC)加盟 | 2. 完全個人開業 | |
|---|---|---|
| 代表例 | とくし丸、セブンあんしんお届け便など | 独自の屋号で、完全に独立して運営 |
| メリット | ・ブランド力で信用を得やすい ・提携スーパーからの商品供給がある ・運営ノウハウの研修を受けられる |
・ロイヤリティがなく、利益率が高い ・仕入れ先や販売商品を自由に決められる ・独自のサービスを展開できる |
| デメリット | ・加盟金やロイヤリティが発生する ・販売エリアやルールに縛られる ・本部の意向に左右される |
・商品仕入れ先の開拓が大変 ・知名度ゼロから顧客開拓が必要 ・全ての経営責任を自分で負う |
例えば、経営や仕入れの経験が全くなく、まずはノウハウを学びながら堅実に始めたい方は「FC加盟」が向いています。
一方、自分で自由に商品を仕入れたり、独自のサービスを展開したりして、より高い利益を追求したい方は「完全個人開業」が選択肢となります。
「自分にも起業できるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。
起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。
「起業して本気で人生を変えたい!と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?
9割が陥る「儲からない移動スーパー」3つの致命的な罠
「移動スーパーは社会貢献にはなるけど、儲からない」。そう思われる事業者がいるのは事実です。
しかし、それはビジネスモデルに問題がある場合が多いです。
多くの真面目な起業家が、知らず知らずのうちにこの罠にハマり、善意だけでは事業を継続できずに廃業に追い込まれています。
その典型的な3つの罠の正体を暴きます。
罠1:【商品ロスの罠】「品揃えの良さ」を追求し、売れ残りの山で赤字に
「お客様に喜んでほしい」という想いから、生鮮食品や総菜を豊富に積み込みたくなる気持ちは分かります。しかし、これが最も陥りやすい罠です。
移動スーパーは、限られたスペースと時間で販売するため、売れ残った商品は「廃棄ロス」となり、そのまま赤字に直結します。
成功している事業者は、過去の販売データに基づき、「この地域では魚より肉が売れる」「この曜日はパンがよく出る」といった売れ筋を徹底的に分析し、無駄な在庫を一切持たない、極めて戦略的な商品構成を組んでいます。
罠2:【非効率ルートの罠】どんぶり勘定で巡回し、ガソリン代と時間だけが無駄に
ただ闇雲に地域を走り回っていても、売上は上がりません。
1日の売上は、「訪問地点数 × 1地点あたりの顧客数 × 顧客単価」で決まります。
儲からない事業者は、この訪問ルートの設計がどんぶり勘定です。
成功する事業者は、地図上に顧客情報をマッピングし、「どの順番で回れば、移動時間を最小化し、販売時間を最大化できるか」という、最適な巡回ルートを常に計算し、改善し続けています。
ガソリン代と時間は、移動スーパーにおける最大のコスト。この効率化なくして、利益は生まれません。
罠3:【ボランティアの罠】「おばあちゃんのため」と安売りし、自分の生活が困窮
お客様との会話の中で、「これもサービスしておくよ」「10円まけとくね」といった安易な値引きや、無料奉仕を繰り返していませんか?
その優しさは尊いですが、ビジネスとしては失敗に繋がりやすいです。
移動スーパーの事業は、ボランティアではありません。
事業を継続し、より多くの人を助け続けるためには、まず自分が、安定した生活を送るための正当な利益を確保する必要があります。
「お客様のため」と「事業の継続」を両立させる、冷静な経営者としての視点がなければ、善意だけではすぐに立ち行かなくなってしまいます。
年商1000万円を安定させる!移動スーパー起業・成功ロードマップ5ステップ
では、どうすれば「儲からない罠」を回避し、社会に貢献しながら、年商1000万円以上を安定的に稼ぐことができるのでしょうか。
ここでは、持続可能な事業へと変えるための、具体的なロードマップを5つのステップで解説します。
このステップに沿って、着実に起業準備を進めていきましょう。
ステップ1:【事業計画と資金調達】移動販売車の費用は?融資を引き出す収支計画
開業には、移動販売車の購入・改造費、商品の初期仕入れ費、当面の運転資金など、個人開業でも最低300万円~500万円程度の資金が必要です。
自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の創業融資などを活用します。融資審査の鍵を握るのが「事業計画書」です。
なぜこの地域で開業するのか(市場調査)。
競合(他のスーパーや生協)とどう差別化するのか。
そして、客数・客単価・訪問頻度から算出した具体的な売上予測と、仕入れ原価や車両維持費を基にした詳細な「収支計画」を提示する必要があります。
ステップ2:【許可申請と仕入れ先確保】保健所の許可と、地域スーパーとの提携交渉
移動スーパーで生鮮食品を含む食料品を販売するには、「食品衛生責任者」の資格を取得し、管轄の保健所から「食品営業自動車」の営業許可を得る必要があります。
この許可を得るためには、車両にシンクや給水・排水タンクなどの設備が必須です。
また、個人開業の場合、最大の課題が商品の仕入れ先です。
現実的なのは、あなたの地域の個人経営のスーパーマーケットと交渉し、パートナーとなることです。
「売れ残りは返品可能」といった柔軟な条件で商品を供給してもらえる関係を築くことが、ロスを減らし、事業を安定させる鍵です。
ステップ3:【巡回ルート設計】儲かる「黄金ルート」を見つけ出す、徹底的な地域調査
事業の成否を分ける、最も重要なステップです。
まずは、開業したい地域の自治体(役所)を訪れ、高齢化率や人口分布のデータを手に入れましょう。
実際にその地域を自分の足で歩き、「スーパーまで遠そうな住宅街」「高齢者だけの世帯が多そうな団地」「車の入れない細い道」などを徹底的にリサーチします。
そして、曜日ごとに訪問するエリアを決め、各訪問地点での滞在時間も考慮した、効率的な巡回ルートを設計します。
この調査が、後の売上を大きく左右します。
ステップ4:【集客戦略】「あなたのスーパー」の到着を、地域中が待ちわびるPR術
巡回ルートが決まったら、営業開始の1ヶ月前から、その地域への集客活動を開始します。
まずは、各訪問地点の掲示板や、地域の回覧板で「〇月〇日から、移動スーパーがやってきます!」というチラシを配布・掲示してもらいましょう。
チラシには、あなたの顔写真と自己紹介、そして「お刺身やお寿司も積んでます!」といった商品の魅力を具体的に記載します。
また、地域のケアマネジャーや民生委員、自治会長に挨拶回りを行い、事業の趣旨を説明し、協力を仰ぐことも極めて有効です。
あなたの訪問を、地域全体で心待ちにしてもらう雰囲気を作り出すのが大切です。
ステップ5:【収益最大化】「ついで買い」を促し、客単価を1.5倍にする商品構成の秘訣
安定した収益のためには、顧客一人あたりの購入金額(客単価)を上げることが重要です。
その鍵は、「ついで買い」を促す商品構成にあります。
例えば、お刺身を買ったお客様には「これに合う醤油やワサビはいかがですか?」と声をかけたり、レジ横に、ちょっとしたお菓子や漬物など、手に取りやすい低価格な商品を置いたりします。
また、「この地域の〇〇さんの畑で採れた、新鮮なトマトですよ」といった、地元の生産者と連携した商品を扱うことも、他にはない付加価値となり、顧客の購買意欲を刺激します。
まとめ:移動スーパーとは、地域の「暮らし」と「笑顔」を運ぶ仕事である
移動スーパーの起業は、地域の食生活というインフラを支え、高齢者の安否を見守り、人々の繋がりと「ありがとう」という笑顔を育み、現代社会になくてはならない誇り高い仕事です。
ボランティアで終わらせることなく、持続可能な事業として成立させていくためには、経営者としての冷静な視点と、ビジネスを成り立たせる強さが不可欠です。
「起業をするのにサポートがほしい」
「起業に必要なことを知りたい」
そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。
ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。
「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?
◯関連記事
・食品製造業起業に必要な資格や設備とは?成功する独立方法5つ
・【起業の集客】もう困らない!お金をかけずに始める、成功への5ステップ