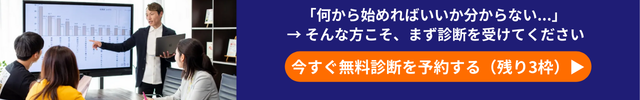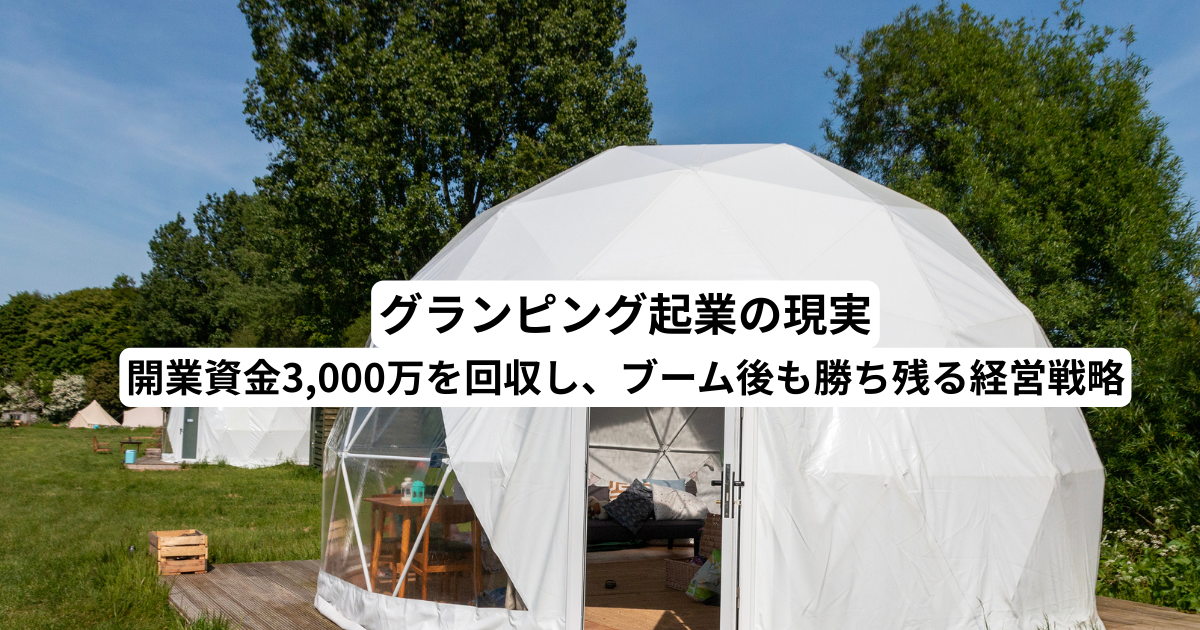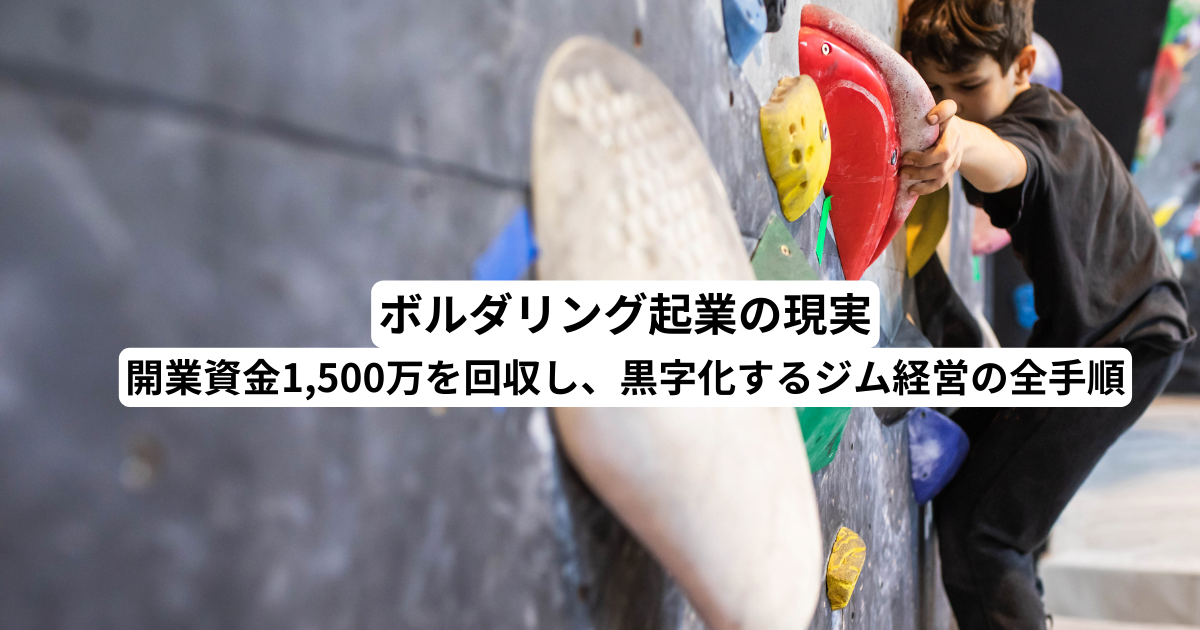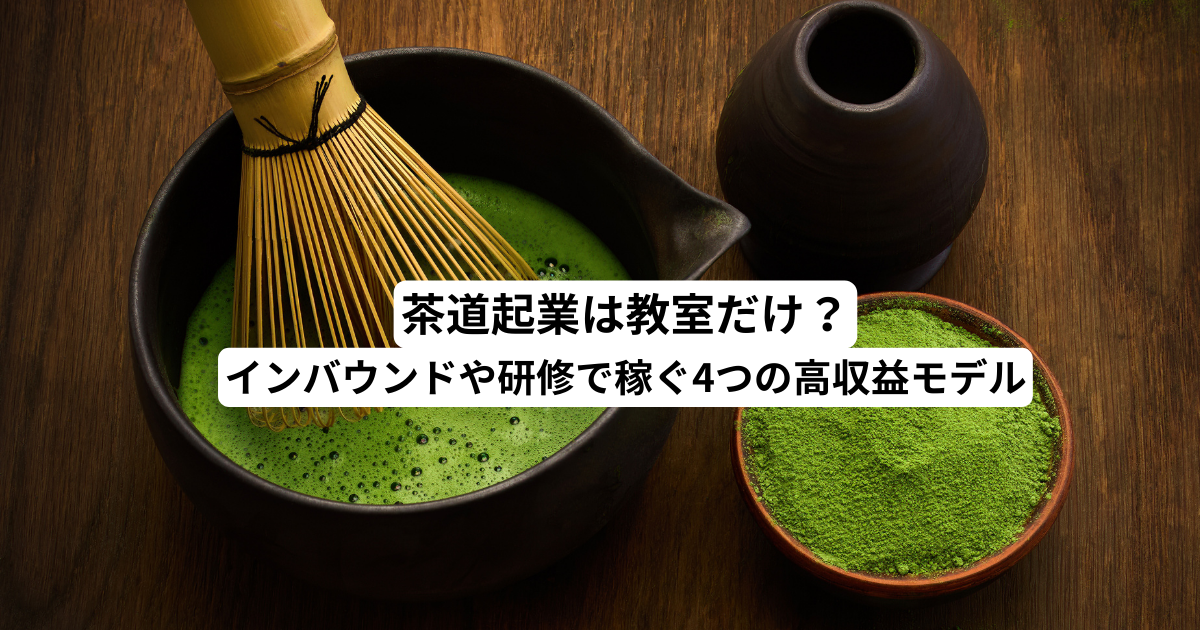2025.10.21 起業ガイド
介護用品レンタルで起業|失敗しない始め方と儲かる経営術
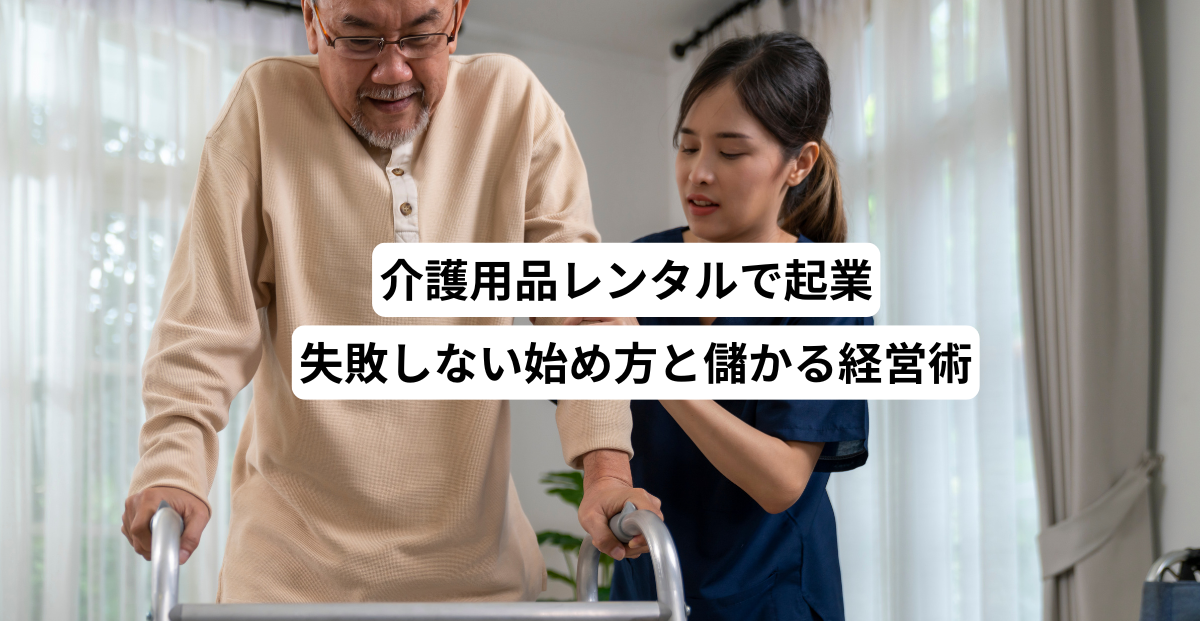
Index
「在宅介護で困っている、お年寄りやそのご家族の力になりたい」
「介護用品レンタルで起業を考えている」
自分の介護経験を活かして、介護用品レンタルでの起業を考えている方はいるのではないでしょうか。
しかし、そもそもどのように起業をしたら良いかわからず、一歩を踏みだせずにいる方もいるかと思います。
そこで今回は、介護用品レンタルでの起業方法やビジネスモデル、具体的な成功ステップを解説します。
この記事を読めば、介護用品レンタルで起業してどのように事業を進めて行けばよいか全体像が掴めます。
なぜ今、介護用品レンタルでの起業が「堅実なビジネス」と言えるのか?
介護用品レンタル起業を今から始めても大丈夫だろうか。と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、介護用品レンタル事業は、他のビジネスにはない成長基盤を持っています。
なぜ、この事業が堅実なビジネスとして成立するのか。理由を3つの視点から解説します。
理由1:超高齢社会がもたらす「なくならない需要」
日本は、国民の4人に1人以上が65歳以上という、世界でも前例のない超高齢社会です。
国は医療費抑制のため、「病院から在宅へ」という方針を強力に推進しており、自宅で介護を受ける高齢者は今後も増え続けます。
それに伴い、在宅介護を支えるベッドや車いす、手すりといった介護用品の需要がなくなることはありません。
流行り廃りとは無縁で、景気の波にも左右されにくい。絶対になくならない市場こそが、介護用品レンタル事業の最大の強みであり、安定性の根拠です。
理由2:介護保険制度に基づく「ストック型収益モデル」
介護用品レンタル事業のほとんどは、介護保険制度を利用して行われます。
利用者はレンタル料の1割(所得に応じて2~3割)を負担し、残りは国保連から事業者へ支払われます。
これにより、事業者は安定した収入を確保できます。
一度レンタル契約を結べば、その用品が必要である限り、毎月継続的に収益が発生する「ストック型」のビジネスモデルです。
毎月の売上の見通しが立てやすく、資金繰りの計画も立てやすい点は、起業する上で大きなメリットです。
理由3:大手にはできない「地域密着」の信頼が武器になる
介護用品は、利用者の身体状況や家屋の環境に合わせ、最適な商品を選定し、安全な使用方法を丁寧に説明する必要があります。
大手企業では難しい、こうした一人ひとりに寄り添った、顔の見えるきめ細やかなサービスこそ、個人事業者の真価が発揮される領域です。
「〇〇さんに頼めば、いつも親身になってくれるから安心だ」。地域での信頼が大手との競争にも負けない強みになります。
【重要】介護用品レンタル起業、3つの指定形態と進むべき道
介護用品レンタル事業を始めるには、行政から「福祉用具貸与事業者」としての指定を受ける必要があります。
この指定の形態は複数あり、どれを選ぶかによって事業の範囲や収益性が大きく変わります。
ここで選択を誤ると、後から変更するのは困難です。それぞれの特徴を正確に理解し、あなたが目指すべき道を定めましょう。
| 指定形態 | 主な事業内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 1. 福祉用具貸与(レンタル)のみ | 介護保険を利用した福祉用具のレンタル事業。 | ・事業の基本となる ・比較的少ない品目で始められる |
・レンタル品目に制限がある ・収益源がレンタル料のみになる |
| 2. 貸与 + 特定福祉用具販売 | レンタル事業に加え、入浴や排泄に関する用具(腰掛便座、入浴補助用具など)の販売も行う。 | ・収益の柱が増える ・利用者への提案の幅が広がる |
・販売品の在庫管理が必要になる ・販売に関する知識も求められる |
| 3. 貸与 + 販売 + 住宅改修 | 上記に加え、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修も請け負う。 | ・客単価が大幅に向上する ・住環境全体をトータルで提案できる |
・建設業の許可が別途必要になる場合がある ・高度な専門知識と施工管理能力が必須 |
結論として、ビジネスとして本格的に収益を上げていきたいのであれば、最低でも「2. 貸与+販売」の指定を目指すべきです。
そして、将来的に「3. 住宅改修」まで事業を広げることで、地域でなくてはならない存在へと成長できます。
指定申請は非常に専門的なので、介護事業専門の行政書士に相談するのがおすすめです。
「法や税的な面で相談に乗って欲しい」「起業するためのサポートが欲しい」など、起業についてのご相談はスタートアップアカデミーにお任せください。
200業種、1000件以上の起業支援を行ってきており、起業のプロから本気のアドバイスを受けられます。
まずは、スタートアップアカデミーの公式LINEから無料の起業相談会にご参加ください。
9割が陥る「儲からない事業者」の3つの致命的な過ち
指定さえ取れば、ケアマネジャーが仕事を紹介してくれる、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、指定事業者は全国に飽和状態で、待っているだけの事業者は淘汰されていきます。
なぜ、多くの事業者が介護用レンタルで起業して、儲からないと言うのか。その根本原因である3つの失敗パターンを解説します。
過ち1:【待ちの営業】ケアマネジャーに「選ばれる理由」がない
失敗する事業者の典型は、「開業しました」と挨拶に行くだけで、あとは紹介の連絡をひたすら待つ「待ちの営業」スタイルです。
多忙なケアマネジャーは、数十、数百の事業者の中からもっとも信頼でき、対応が迅速で、専門性の高い事業者を選びます。
「他の事業者にはない、どんな強みがあるのか」「どんな専門知識を持っているのか」が明確になっているかが重要です。
過ち2:【単一収益】「レンタル料」だけで稼ごうとし、利益を取りこぼす
介護用品レンタル事業の収益は、介護保険のレンタル料だけではありません。
むしろ、そこから先の自費サービスにこそ、大きな利益の源泉があります。
例えば、保険適用外の便利な商品の提案、利用者宅の片付けや電球交換といった「お困りごとサポート」、通院時の付き添いサービスなどです。
「ついでのお願い」に適切な料金を設定して応えることで、客単価は2倍、3倍にもなり得ます。
レンタル料だけで利益を出そうとすると、事業は必ず行き詰まります。
過ち3:【在庫・衛生管理の甘さ】コスト増と信頼失墜を招く
介護用品レンタルは、商品を仕入れて貸し出す、在庫ビジネスです。
どの商品を、何台仕入れるか。需要予測を誤れば、使われない在庫が倉庫で眠り続け、資金を圧迫します。
また、返却された用具の消毒・メンテナンスといった衛生管理は、事業の生命線です。
ここで手を抜けば、感染症などの重大な事故に繋がり、一瞬で信頼を失い、事業停止に追い込まれます。
目に見える営業活動だけでなく、裏側の地道な管理業務の徹底が、事業の継続性を左右します。
月収50万を安定させる!介護用品レンタル起業・成功ロードマップ
では、どうすれば失敗の罠を避け、社会に貢献しながら、月収50万円以上を安定的に稼ぐことができるのでしょうか。
ここでは、持続可能な儲かる事業へと変えるための具体的な5つのステップを解説します。
ステップ1:【事業計画と資金調達】融資を引き出す「勝てる計画書」の作り方
介護レンタル用品起業には、福祉車両の購入や商品の仕入れ、事務所の敷金礼金、当面の運転資金など、最低でも500万円~1,000万円の資金が必要です。
自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の創業融資などを活用します。
融資審査の鍵を握るのが事業計画書です。なぜこの地域で起業するのか、競合とどう差別化するのか、そして、利用者数を何人獲得すれば黒字化できるのか。
これらの要素を、具体的な数字で資料にまとめる必要があります。
ステップ2:【法人設立と指定申請】最短ルートで「福祉用具貸与事業者」になる
介護用品レンタルで起業するには、都道府県から「福祉用具貸与事業者」の指定を受ける必要があります。
この指定を受けるためには、法人格を持つことが必須です。
まずは株式会社または合同会社を設立しましょう。
同時に、事業所に常勤で配置する必要がある「福祉用具専門相談員」の資格を取得します(介護福祉士などの資格があれば講習免除)。
法人設立と並行して、専門家の助言を受けながら指定申請書類の準備を進めるのが、起業までの最短ルートです。
ステップ3:【商品仕入れと管理体制】失敗しない最初の在庫構成とは?
最初から全ての商品を揃える必要はなく、まずは、もっとも需要の高い「特殊寝台(介護ベッド)」や「車いす」「歩行器」「手すり」といった基本商品に絞って、数台ずつ仕入れましょう。
仕入れ先は、メーカーや卸問屋と直接契約します。
同時に、返却された商品を洗浄・消毒し、保管するための衛生管理マニュアルと、在庫の稼働状況を管理する仕組みを構築します。
ステップ4:【仕事の取り方】ケアマネに「あなたを指名させる」最強の営業術
仕事の獲得は、地域の居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属)や、地域包括支援センター、病院のソーシャルワーカーへの営業が中心です。
ただ名刺を配るのではなく、「私は〇〇(例:褥瘡予防)の専門知識があります」「24時間365日、緊急対応可能です」といった、あなたの強みを明確に伝えましょう。
また、ケアマネジャーが利用者に提案しやすいように、写真付きで分かりやすい商品カタログや、専門知識をまとめた情報紙などを定期的に届けることも、信頼関係を築く上で非常に有効です。
ステップ5:【収益最大化】運賃以外の「保険外サービス」メニューを作る
レンタル料以外の収益の柱を立てましょう。
まずは、利用者の「ちょっとした困った」に応える「保険外サービスメニュー」を作成し、料金表として明示します。
例えば、「電球交換・家具の移動:15分 1,000円」「買い物代行:1回 2,000円+実費」「通院付き添い:30分 1,500円」などです。
これらのサービスは、利用者やその家族から非常に喜ばれ、あなたの事業所のファンを増やすと共に、収益を大きく向上させます。
介護保険の枠にとらわれず、顧客のニーズに柔軟に応える発想が重要です。
まとめ:介護用品レンタルとは、利用者の「在宅生活」を支えるインフラである
介護用品レンタルでの起業は、高齢者や障がいを持つ方が、住み慣れた自宅で、安全に自分らしく暮らし続けることを支える、地域社会にとって重要な仕事です。
ぜひ、この記事を参考に介護用品レンタル起業へ一歩を踏み出してみませんか?
「この事業が本当に成り立つのか、客観的な意見が欲しい」
「起業して事業が軌道にのるまでサポートして欲しい」
スタートアップアカデミーでは、公式LINEから無料の起業相談会を行っています。
この相談会にご参加いただければ、どのようにビジネスを形にしていくか、何をするべきなのかが明確になります。
事業の立ち上げをしっかり伴走させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
◯関連記事
・【福祉で一人起業】アイデア5選|資格なしOK?資金と成功の秘訣
・福祉タクシーで起業|失敗しない開業と月収50万稼ぐ経営術