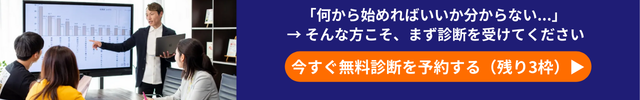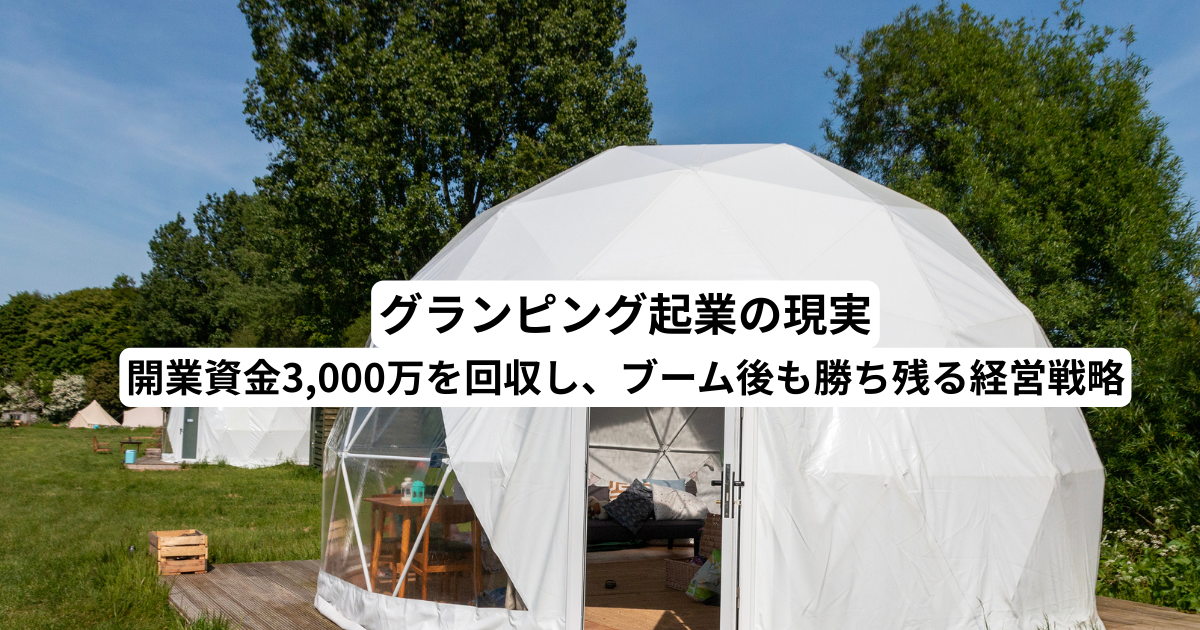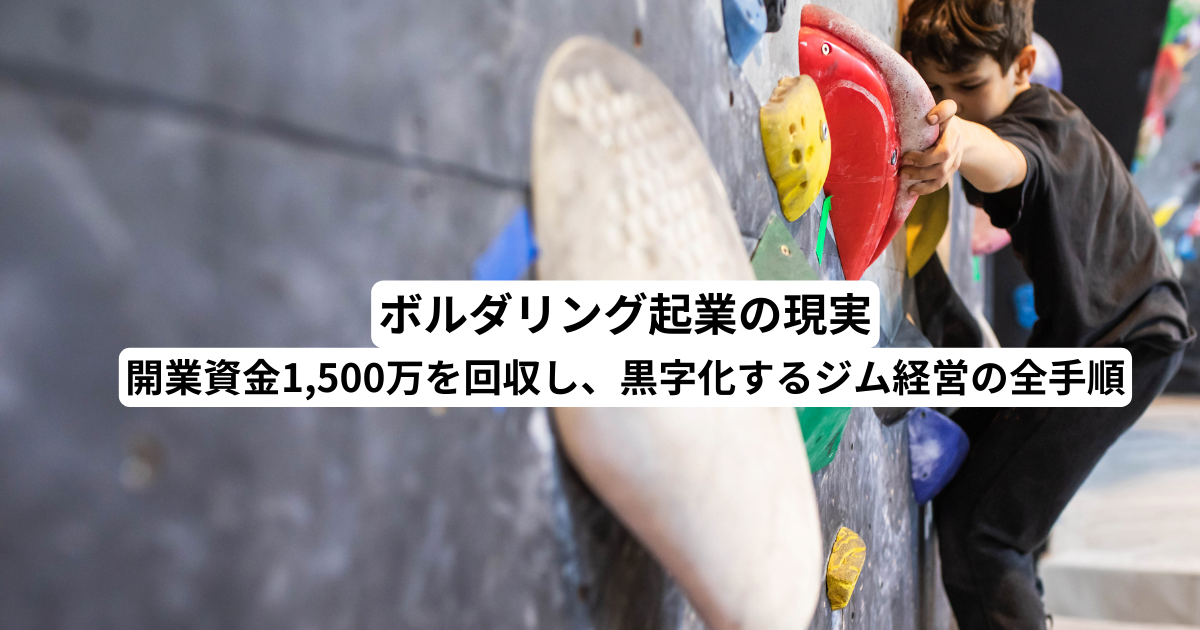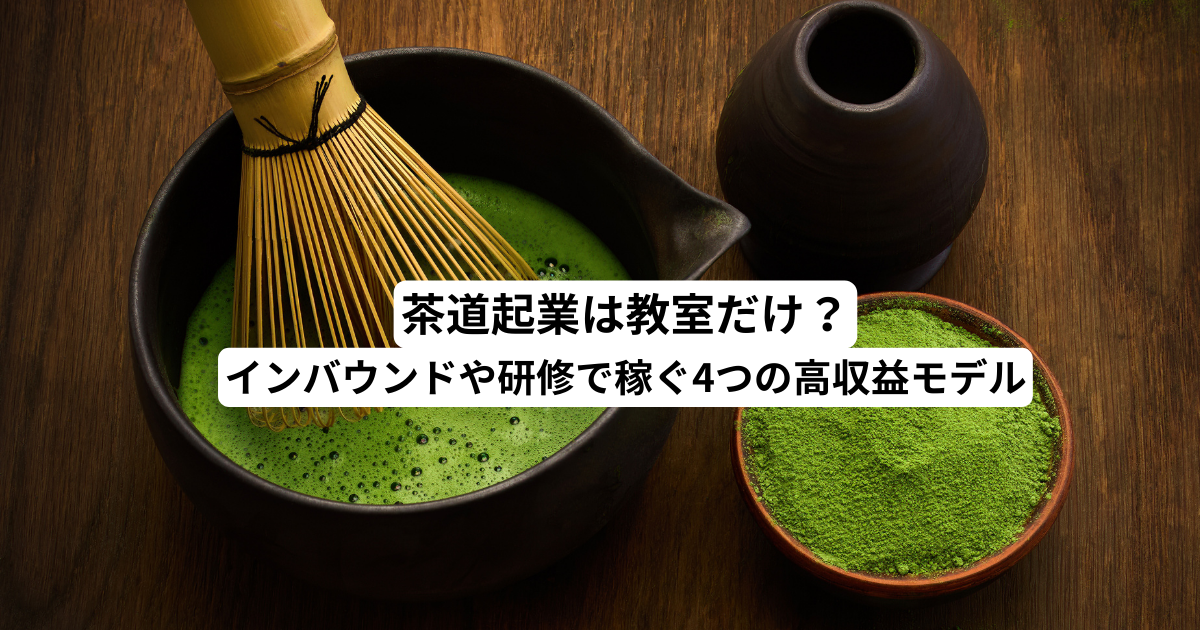2025.08.16 起業ガイド
【福祉で一人起業】アイデア5選|資格なしOK?資金と成功の秘訣

Index
「もっと、一人ひとりに寄り添ったケアがしたい」
「制度の壁を越えて、本当に必要なサービスを届けたい」。
福祉の現場で働く方なら、一度はこのような想いを抱いたことがあるのではないでしょうか。福祉の分野で一人起業を考えている方もいるはずです。
今回は、制度ビジネスや自由なサービス、一人で始められる福祉事業のアイデアと、その夢を持続可能なビジネスに変えるための具体的なステップを解説します。
この記事を読めば、自分がどのような福祉ビジネスを始めたらよいかがわかります。
あなたはどっち?福祉起業の2つの道筋

福祉分野で一人起業を考えるときに、進むべき道は大きく2つに分かれます。
一つは国や自治体のルールに則って安定した収益を目指す「制度ビジネス」
もう一つは、自由な発想で新しい価値を提供する「保険外サービス」です。
どちらが優れているというわけではなく、自分の想いや経験、目指す姿によって道は異なります。
まずはこの2つの道筋の違いを理解し、自分の進むべき方向性を見定めましょう。
| 道筋1:介護保険事業(制度ビジネス) | 道筋2:保険外サービス(自由市場) | |
|---|---|---|
| 具体例 | 訪問介護、居宅介護支援、介護タクシー | 高齢者向け家事代行、見守り、趣味活動支援 |
| メリット | 介護保険から報酬が得られ、収入が安定しやすい | 価格やサービス内容を自由に決められる |
| デメリット | 人員・設備基準など、開業・運営のルールが厳しい | 集客や値付けを全て自分で行う必要がある |
| 向いている人 | 安定した経営基盤を築きたい人、制度のプロ | 新しい価値を創造したい人、マーケティングが得意な人 |
安定を求めるなら制度ビジネス、自由を求めるなら保険外サービスが一つの目安です。両方を組み合わせるハイブリッド型も可能です。
例えば、訪問介護事業所を運営しながら、保険ではカバーできない自費の同行援護サービスの提供。ハイブリッド型にすると、さまざまな組み合わせでビジネスの幅が広がります。
今すぐできるアクション:
あなたが解決したい「社会の課題」と、あなたが提供したい「独自の価値」を紙に書き出し、どちらの道筋がより想いを実現しやすいか考えてみましょう。
一人で始められる福祉・介護の起業アイデア5選

一人で始められる福祉ビジネスで、「具体的にどんなビジネスがあるの?」という疑問にお答えします。
ここでは、一人でもスモールスタートが可能な、5つの具体的な起業アイデアをご紹介します。自分の経験や資格、興味関心と照らし合わせながら、可能性を探ってみてください。
アイデア1:訪問介護事業所|地域に根ざしたケアの実現
利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生活援助を行う、これは代表的な介護保険事業です。法人格が必要で、管理者やサービス提供責任者といった人員基準がありますが、一人で兼務することも可能です(要件あり)。
地域との連携は不可欠で、ケアマネージャーと信頼関係を築くことが成功の鍵。
地域に深く根ざし、利用者様の在宅生活を支えたいという想いが強い方に向いています。
アイデア2:介護タクシー(福祉輸送)|移動の自由を支える
車椅子やストレッチャーのまま乗車できる車両を使い、高齢者や障害者の移動をサポートする仕事です。
開業には「第二種運転免許」や「介護職員初任者研修」などの資格、そして運輸局の許可が必要です。
通院だけでなく、買い物や旅行といった「生活の楽しみ」を支えることができる、非常にやりがいのある仕事です。運転が好きで、人の外出をサポートしたい方におすすめです。
アイデア3:保険外の自費サービス|制度の隙間を埋める
介護保険ではカバーできない、しかしニーズの高いサービスを自由に提供するビジネスです。
例えば、高齢者向けの「スマホ教室」や「電球交換や庭の手入れといった御用聞きサービス」「ペットのお世話代行」や「話し相手サービス」など、アイデアは無限大。
許認可が不要な場合が多く、低リスクで始められるのが魅力。
地域の「ちょっとした困りごと」に気づき、解決するのが得意な方に向いています。
アイデア4:障害者グループホーム|小規模で家庭的な暮らしの場
障害を持つ方が、世話人などのサポートを受けながら共同生活を送る住居。サテライト型住居など、一人でも運営しやすい形態が登場しています。
家賃収入と訓練等給付費が主な収益源となり、安定した経営が見込めます。利用者の自立を支援し、家庭的な雰囲気の中で「第二の家族」のような存在になりたいと考える方に最適です。
アイデア5:福祉・介護専門のコンサルタント/研修講師
あなたが現場で培ってきた豊富な経験や知識自体も、価値ある商品になります。
例えば、介護事業所向けの「人材育成コンサルティング」や「虐待防止研修」、あるいは介護職を目指す人向けの「資格取得支援講座」など。
自分の専門性を活かし、業界全体の質を向上させたいという高い志を持つ方にぴったりの仕事です。
福祉起業を成功させる5つのステップ【事業計画】

やりたい事業の方向性が決まったら、次は想いを具体的な事業計画に落とし込んでいきます。
この設計図の精度が、あなたの起業の成功確率を大きく左右します。
ステップ1:コンセプト設計|誰の、どんな「困りごと」を解決するか
なぜ、あなたの事業が必要なのでしょうか?
「誰の、どんな『不便』や『不満』を解決するのか」を、一言で説明できるようにしましょう。
例えば、「一人暮らしの高齢者の、買い物に行けないという『不便』を解決する」「日中独居の認知症高齢者を抱える家族の、『不安』を解消する見守りサービス」など。
コンセプトが明確であればあるほど、あなたの事業は社会から必要とされます。
ステップ2:事業計画・資金計画|想いを数字と計画に落とし込む
コンセプトを、具体的な数字と行動計画に落とし込みます。
提供するサービス内容や価格設定、売上目標、そして開業に必要な初期費用(物件取得費、車両購入費など)と、月々の運転資金(人件費、家賃、ガソリン代など)を詳細に算出します。
計画書は、融資を受ける際にも必要なプレゼン資料となります。
ステップ3:法人格の選択|株式会社か、NPO法人か
福祉事業を行う場合、個人事業主として始める他に「株式会社」や「合同会社」「NPO法人」といった法人格を取得する選択肢があります。
介護保険事業の指定を受けるには、原則として法人格が必要。社会的信用を重視し、利益を追求するなら株式会社。
非営利性と社会貢献を前面に出すならNPO法人など、それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたの事業理念に合った形態を選びましょう。
ステップ4:資格・人員・設備基準の確認と許認可申請
行う事業によって、必要な資格や人員、設備の基準は法律で厳しく定められています。訪問介護なら「介護福祉士」の資格を持つサービス提供責任者の配置が必須です。
都道府県や市町村に申請して「指定」や「許可」を受けなければ事業を開始できません。行政書士などの専門家に相談しながら、確実に準備を進めましょう。
ステップ5:資金調達と集客準備|融資とケアマネ営業
自己資金だけで足りない場合は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、自治体の制度融資を活用します。
福祉分野は社会性が高いため、比較的融資を受けやすい傾向にあります。
資金調達と並行して、集客の準備も始めます。特に介護保険事業の場合、お客様を紹介してくれる地域のケアマネージャーへの挨拶回り(営業活動)が、事業の生命線となります。
私たちLCSでは起業コンサルを行っています。LINE登録から、無料の企業相談を受けられます。ぜひお気軽にLINEでご相談ください。
福祉起業の前に知るべき「資格」と「資金」のリアル

「資格がないとダメ?」「お金はいくら必要?」この2つは、福祉起業を志す方が抱える最大の不安です。
次はリアルな実情について解説します。
必要な資格は事業による|「資格なし」でも起業は可能か?
結論から言うと、資格なしでも福祉分野での起業は可能。
特に、保険外の自費サービス(家事代行、見守りなど)は、特別な資格がなくても始められます。
ただし、訪問介護や介護タクシーなど、介護保険法に基づく事業や、人の身体に触れるサービスを行う場合は、「介護福祉士」や「介護職員初任者研修」「第二種運転免許」などの資格が必須となります。
資格はお客様からの信頼を得る上でも強力な武器になります。
開業資金はいくら?モデルケース別シミュレーション
開業資金は、事業内容によって大きく異なります。
| 事業モデル | 初期費用目安 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 保険外サービス(自宅事務所) | 10〜50万円 | PC・備品購入費、広告宣伝費 |
| 訪問介護事業所(小規模) | 150〜300万円 | 法人設立費用、事務所賃借料、備品、人件費 |
| 介護タクシー | 200〜500万円 | 福祉車両購入費、法人設立費用、駐車場代 |
これはあくまでモデルケースですが、工夫次第で費用を抑えることは可能。中古の福祉車両を探したり、事務所はシェアオフィスを活用したりするなどです。
しかし、一番重要なのは、初期費用とは別に、事業が軌道に乗るまでの運転資金(ご自身の生活費含む)を最低でも3ヶ月分、理想は半年分準備しておくことです。
売上がすぐに入金されるとは限らないため、この「守りの資金」が生命線となります。
自己資金ゼロでも可能?福祉分野に強い融資・補助金活用術
自己資金がゼロでも、諦める必要はありません。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、各自治体の創業支援融資は、自己資金要件が緩和されるケースがあります。
また、福祉分野は社会貢献性が高いため、「地域創造的起業補助金」や、返済不要の補助金・助成金の対象となることもあります。
地域の商工会議所や行政の窓口へ行き、最新の情報を収集しましょう。
まとめ:福祉起業は、社会を良くするビジネス

福祉分野での一人起業は、単にお金を稼ぐこと以上の、大きな社会的意義を持つ挑戦です。自分の経験と想いは、誰かの「生きがい」や「安心」に直接つながります。
想いを持続させるためには、事業を安定させる「経営」の視点が不可欠です。ぜひ、この記事の内容を実践して一歩踏み出してみましょう。
その専門的な悩み、一人で抱え込まないでください。
私たちの公式LINEを登録すると、無料の起業相談を行えます。どんな細かい悩みでも構いません!ぜひLINEからお気軽にご相談ください。
起業に役立つ特典もプレゼントしているので、ぜひLINEを登録してみてください。
◯関連記事
・【起業して軌道に乗るまで】3年間のリアルな道のりと乗り越えるための全戦略
・起業の準備期間は平均1年?最短で独立するための7ステップと成功ロードマップ