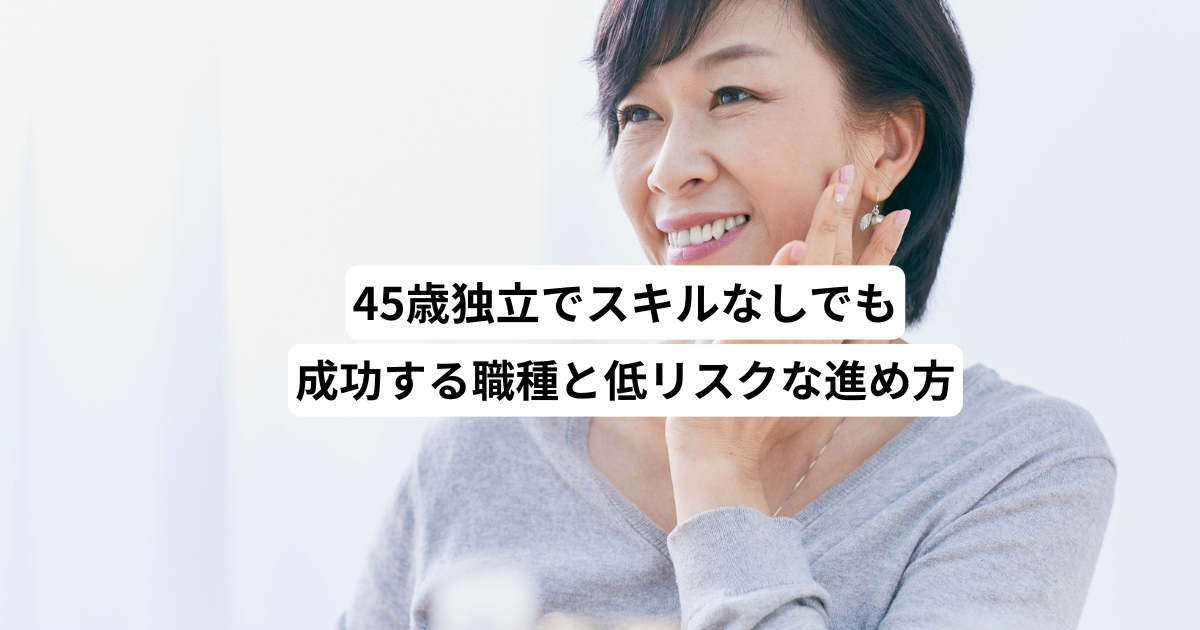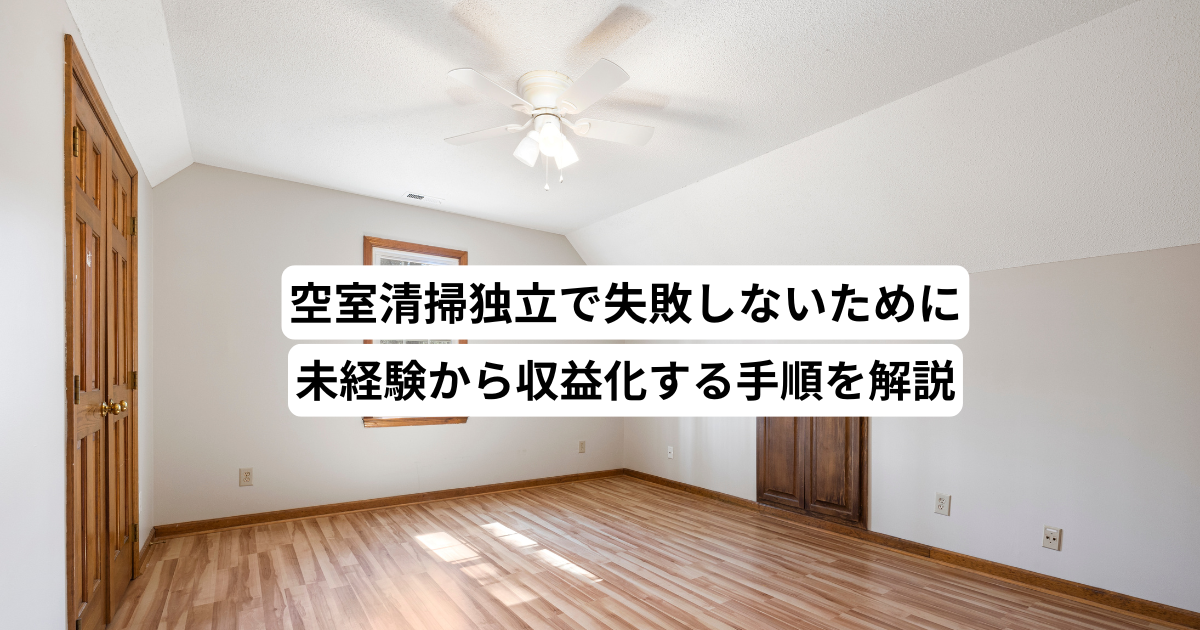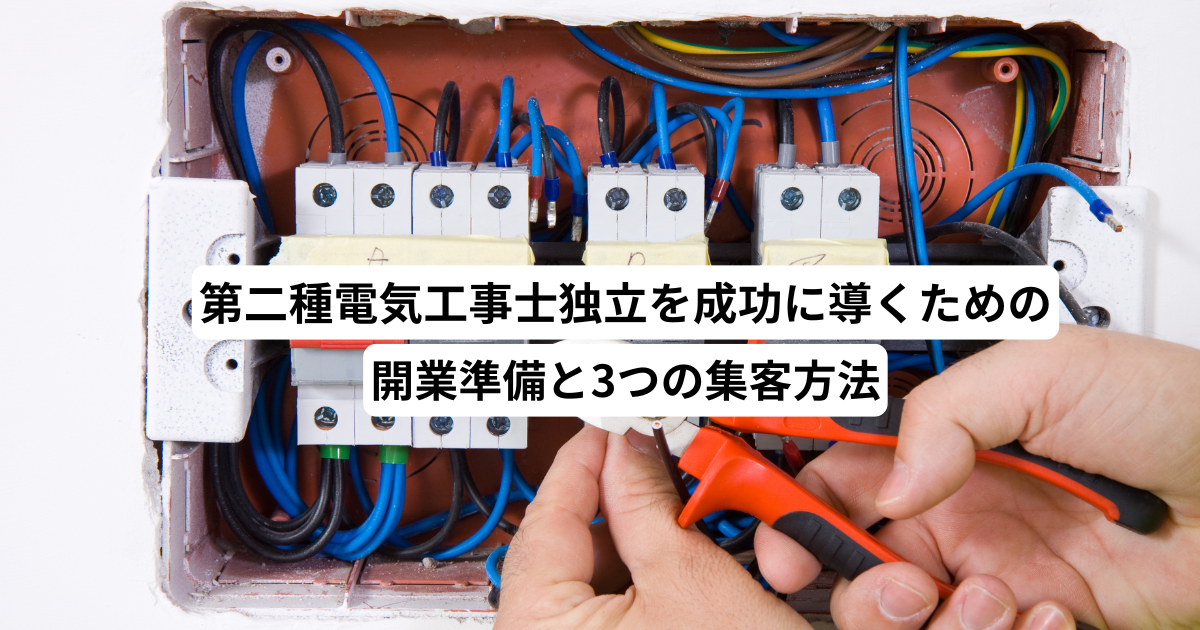2025.11.06 起業ガイド
食品製造業起業に必要な資格や設備とは?成功する独立方法5つ

Index
「こだわりのレシピで、いつか自分の食品ブランドを立ち上げたい」
「食品製造業界での経験を活かして、地域の人に喜ばれる安全な食品を届けたい」
食品製造業での起業に憧れながらも、「経営は未経験」「設備投資や運転資金は、どれくらい必要なのだろう」など、多くの不安を抱えているのではないでしょうか。
本記事では、あなたの食品製造業での経験を活かしながら、起業を成功に導くための具体的な「5つのポイント」を分かりやすく解説します。
最後まで読めば、具体的な行動計画が立てられ、食品製造業での独立に向けて、着実なステップが歩めます。
食品製造業起業の成功には計画と準備が必要
あなたの持つ食に関する知識は、食品製造業起業で活かせるスキルです。
しかし、美味しいものを作る技術と、事業を継続させて利益を生み出す経営は異なります。
やる気や感覚だけに頼るのではなく、事業を始める前の入念な計画と準備こそが、起業を成功へ導くためには必要です。
1. 食品製造業起業前に資格と営業許可を調べる
食品製造業を始めるために、最初に着手すべきは法的な要件の確認です。
消費者に安全な食を届けるという社会的責任を果たすため、資格取得や許可申請が法律で定められています。
食品衛生責任者の取得
食品を扱う施設には、必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。
これは、施設における衛生管理の責任者となるための資格です。
資格取得は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講することで可能です。
講習は1日で完了することが多く、比較的取得しやすい資格といえます。
まずはこの資格を取得することが、食品製造業を始めるうえで必要になります。
営業許可の種類と取得
製造・販売する食品の種類によって、必要な営業許可は異なります。
例えば、菓子を製造する場合は「菓子製造業」、食肉製品を作るなら「食肉製品製造業」の許可が必要です。
これらの許可は、施設の設備が定められた基準を満たしていることを、管轄の保健所が確認したうえで交付されます。
どのような許可が必要になるか、必ず施設の工事を始める前に、管轄の保健所へ事業内容の相談に行くことが重要です。
HACCPに沿った衛生管理
HACCPとは、食品の製造工程における危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視・記録することで、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。
また、2021年6月から、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
小規模な事業者であれば、手引書を参考にした簡易なアプローチも認められています。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画を作成し、実行・記録することが、食品製造業の起業には求められます。
独立に必要な設備投資を含むリアルな事業計画の作成
自己資金はいくらあるか、どのような設備にいくら投資するのか、毎月の運転資金はどれくらいか。
これらを具体的にまとめたものが事業計画です。特に日本政策金融公庫などから融資を受ける場合、事業計画書が審査通過のポイントとなります。
自身の経験ややる気を伝えるだけでなく、売上予測や利益計画などを具体的な数字で示し、返済能力を客観的に証明することが不可欠です。
2. 食品製造業起業は経験を売れるブランドのコンセプト設計が必要
食品製造業で起業しても優れた調理技術があるだけでは、商品は売れません。
数ある食品の中から顧客に選んでもらうためには、「なぜあなたの商品を買うべきなのか」を明確に伝えるブランドコンセプトが不可欠です。
この設計が、今後の商品開発から販路開拓まで、すべての活動の指針となります。
独立した個人メーカーだからこそできる熱狂的なファン作り
食品製造業では大企業と同じ土俵で価格競争をしても勝ち目はありません。
個人メーカーの強みは、作り手の顔が見えること、そして商品に込められたストーリーです。
なぜこの商品を作ろうと思ったのか、どんな素材にこだわっているのか。
製造した製品の背景にあるあなたの熱意やストーリーを、SNSや商品パッケージを通じて積極的に発信することが、共感を呼び、熱狂的なファンを作る方法となります。
「こだわり」と「利益」を両立させる商品開発と原価計算
良い商品を作りたいという想いが強いほど、原価が高騰してしまう傾向があります。
しかし、ビジネスとして食品製造業を継続するためには、適正な利益の確保が不可欠です。
まずは、商品の販売価格をいくらに設定したいかを考え、そこから逆算して許容できる原価を算出します。
そのうえで、こだわりたい部分とコストを抑える部分にメリハリをつけ、利益確保が可能な商品設計を行うことが重要です。
3. 食品製造業の開業には安全と効率を両立する一人工場が必要
ブランドのコンセプトが決まり、商品の方向性が見えたら、次はそれを形にするための「工場」、つまり製造場所を確保します。
食品を製造する場所は、ただ調理ができれば良いわけではありません。
食品衛生法で定められた基準をクリアし、保健所から営業許可を取得できる施設であることが条件です。
「私にもできるか不安…」「まずは話だけ聞きたい」と思っている方もいるでしょう。
起業スクールのスタートアップアカデミーは、公式LINEで起業に役立つ特典やコンテンツの配信、無料起業相談会も実施しています。
「起業して本気で人生を変えたい!と思う方は、まずは一歩踏み出してみませんか?
営業許可がとれる製造場所の条件
食品製造業の起業では、営業許可を取得するための、施設設備が基準を満たしている必要があります。
例えば、「床や壁は清掃しやすい不浸透性の素材である」「シンクは用途別に複数設置されている」「十分な換気設備がある」「従業員用の手洗い設備がある」など、細かい規定があります。
住居スペースと製造場所の入口が別であるなど、生活空間と明確に区画されていることも求められるため注意が必要です。
レンタルキッチンを選択するのも有効
自宅の改築やテナントを借りての設備投資は、数百万円単位の資金が必要になることもあります。
有効な選択肢となるのが、菓子製造業などの営業許可を取得済みの「レンタルキッチン」の活用です。
月額数万円程度から利用できる施設も多く、初期費用を大幅に抑えながら、すぐに食品製造をスタートできるメリットがあります。
まずはレンタルキッチンで始め、事業が軌道に乗ってから自前の工場を構えるのも賢明な判断です。
4. 食品製造業起業には、作った商品を販売する販路も必要
どれだけ素晴らしい食品を製造しても、顧客の元に届かなければ売上にはつながりません。
商品をどのようにして販売するのか、販路の確保は、製造体制を整えるのと同じくらい重要な課題です。
オンラインとオフラインの販路比較
オンラインの代表は、BASEやSTORESなどで手軽に開設できるネットショップです。
全国の顧客にアプローチできる一方、集客は自分で行う必要があります。
オフラインで考えられるのは、地域のマルシェやイベントへの出店です。
顧客と直接コミュニケーションが取れる楽しさがあるものの、天候に左右されるなどの側面もあります。
食品製造業の起業では、オンラインとオフラインを組み合わせ、多角的な販路を試すことがリスク分散につながります。
SNSや地域コミュニティを活用した集客術
広告費をかけられない個人のメーカーにとって、SNSは無料で始められる強力な集客ツールです。
商品の写真だけでなく、製造工程の裏側や、商品開発に込めた想いなどを発信することで、ブランドのファンを育てられます。
また、地域のイベントへの参加や、地元の商店に商品を置いてもらうなど、地域コミュニティとのつながりを深めることが、信頼と口コミを生むきっかけになります。
魅力が伝わるパッケージと食品表示の作り方
食品製造業で製造した商品のパッケージは、魅力を伝える「顔」であり、顧客が最初に目にする重要な部分です。
ブランドイメージに合ったデザインで、商品の価値を一目で伝えられる工夫が求められます。
同時に、パッケージには法律で定められた「食品表示」を記載する義務があります。
原材料名、アレルギー表示、賞味期限、栄養成分表示など、食品表示法で定められた項目を、消費者に分かりやすく正確に記載することが必要です。
5. 食品製造業の起業で経営未経験でも利益を出し続ける仕組みづくり
食品製造業として事業を始めること以上に、継続させ、利益を出し続けることの方がはるかに困難です。
特に経営未経験の場合、日々の製造に追われ、お金の管理や事業全体の運営がおろそかになりがちといえます。
感覚に頼った経営ではなく、データに基づいた判断ができる仕組みを構築することが、事業を長く続けるためのポイントです。
一人社長の生産・在庫管理術
食品を扱ううえで避けられないのが、賞味期限の管理と食品ロスの問題です。
食品製造業で作りすぎは廃棄が増えて利益を圧迫し、少なすぎれば販売機会を逃してしまいます。
この問題を解決するには、日々の売上データを記録・分析し、需要を予測する習慣が不可欠です。
過去の販売データや季節のイベントなどに基づいて、無理のない生産計画を立てることが、食品ロスの削減や利益の安定につながります。
次のヒット商品を生むための改善サイクル
一度ヒット商品が生まれても、それに安住していては食品製造業は成長しません。
市場のニーズや顧客の好みは常に変化しています。
イベントで直接顧客の声を聞いたり、ネットショップのレビューを分析したりして、常に改善のヒントを探し続ける探究心が必要です。
お客様から得たフィードバックを真摯に受け止め、次の商品開発や既存商品の改良に活かす仕組みを意識的に作ることが、長く愛されるブランドを育てることにつながります。
まとめ:食品製造業起業は事前準備と設立後の改善サイクルがポイント
食品製造業での起業は、多くの準備と知識が必要であり、決して簡単とはいえません。
しかし、本記事で解説した「5つのポイント」である①〜⑤を、ていねいに進めることで、食品製造業起業の成功率は上がります。
あなたの持つ素晴らしい経験を、計画的な準備と継続的な改善サイクルに乗せて、多くの人に「美味しい」を届けるという夢を実現させてください。
「起業をするのにサポートがほしい」
「起業に必要なことを知りたい」
そんなお悩みもあるかと思います。スタートアップアカデミーでは、公式LINEで無料相談会を実施しています。
ほかにも起業に役立つ特典のプレゼントやコンテンツの配信も実施しています。
「起業をしてみたい!」と思っている方は、ここから一歩踏み出してみませんか?
◯関連記事
・【今からタピオカで起業?】ブーム後に「勝ち残る」新戦略と始め方
・【週末起業】キッチンカーは儲かる?失敗しない始め方とリアルな収支